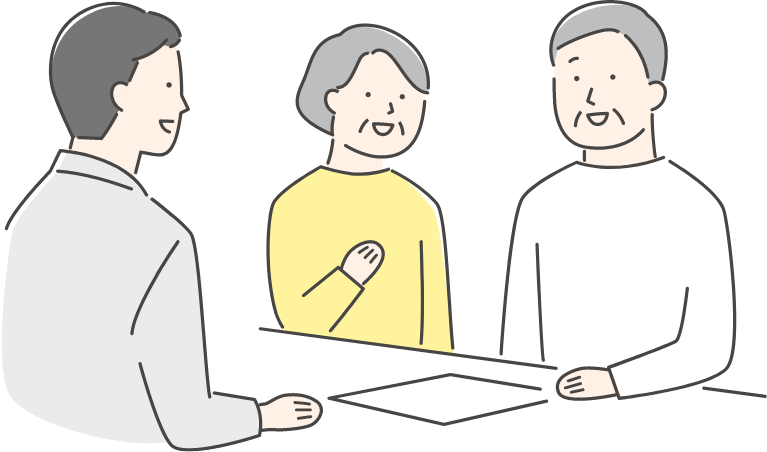
1分ですぐわかる
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
Q1
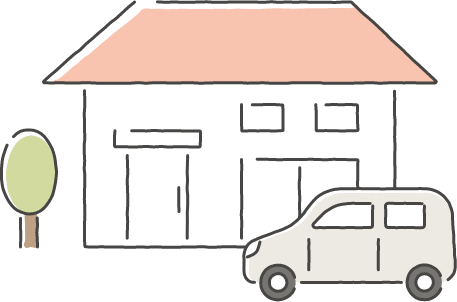
一軒家ですか?
Q2

4.5畳以上の部屋が
ありますか?
ありますか?
Q3
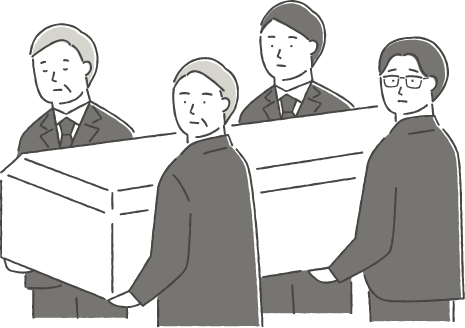
棺の出入りが可能ですか?
(棺サイズ:200cm×60cm)
(棺サイズ:200cm×60cm)
Q4
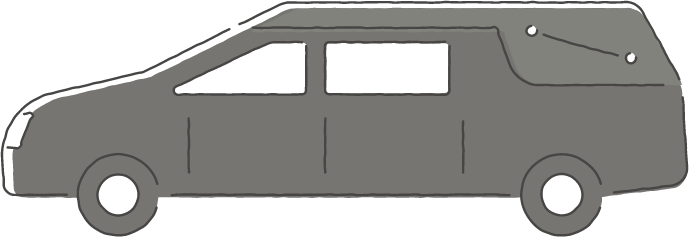
霊柩車が停められる
スペースがありますか?
スペースがありますか?
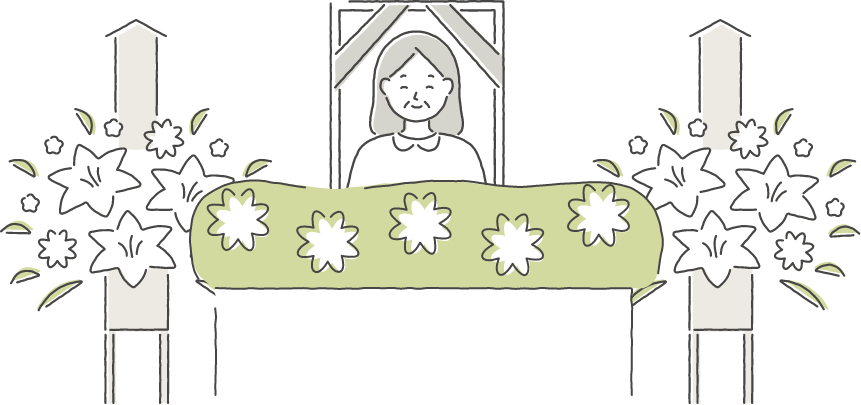
自宅葬が可能です。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

ご相談ください。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
仏事の豆知識

この品は、故人を偲ぶために参列してくれた方々への感謝の意を込めたものであります。
また法事だけでなく、香典返し(満中陰志)の事を「茶の子」という地域もございます。
広島では法事のお返しや香典返しをそのまま「茶の子」とよばれるようになりました。
法事のお返しや香典返しでは結びきりの黄白色の水引を使用します。
また香典返しについては「満中陰志」や「粗供養」と記載しても良いです。
県外の方に香典返しを送る場合茶の子では通じない場合もありますので、その場合は「志」や「満中陰志」「粗供養」で記載する方が良いでしょう。
法事でもらう「茶の子」って何?広島県の法事の文化[自宅葬のサトリエ]
2025年04月02日はじめに
広島県の法事に出席すると、帰りに「茶の子」と呼ばれる品をもらうことがあります。この「茶の子」とは一体何なのか?そして、広島県における法事の文化はどのような特徴を持っているのかについて掘り下げてみましょう。この記事では広島県独自の法事文化について触れ、広島県のご法事の参考にして頂ければ幸いです。茶の子とは?
「茶の子」とは中国地方、特に広島県で一般的に用いられる言葉で、法事や葬儀の際に参列者に贈られる返礼品のことを指します。
この品は、故人を偲ぶために参列してくれた方々への感謝の意を込めたものであります。
また法事だけでなく、香典返し(満中陰志)の事を「茶の子」という地域もございます。
茶の子の中身
一般的に、「茶の子」には以下のような品物が含まれます。- お茶 お茶は賞味期限も長く日常的に使用する事から、昔から好まれております。
- お菓子 もなかや羊羹、せんべいといった保存がきく和菓子が選ばれることが一般的です。
- 果物 季節の果物が含まれることもあり、新鮮さを大切にする風習が見られます。
- 海苔や佃煮 保存が効き、ご飯と一緒に食べられるものが多く選ばれます。
茶の子の由来と意味
「茶の子」の由来については諸説ありますが、全国的にはお茶にそえるお茶菓子を茶の子と言ったり、お茶菓子をのせる半紙などの「かえし」の事を「茶の子」と言います。広島では法事のお返しや香典返しをそのまま「茶の子」とよばれるようになりました。
茶の子の水引は?
茶の子の水引については、通常の作法と同様です。法事のお返しや香典返しでは結びきりの黄白色の水引を使用します。
茶の子以外はどんなものがある?
茶の子以外で一般的には「志」と記載する場合が多くなっております。また香典返しについては「満中陰志」や「粗供養」と記載しても良いです。
県外の方に香典返しを送る場合茶の子では通じない場合もありますので、その場合は「志」や「満中陰志」「粗供養」で記載する方が良いでしょう。








![法事でもらう「茶の子」って何?広島県の法事の文化[自宅葬のサトリエ]の画像](/image.php?t=webp&w=600&p=/sys_blog/202504/E88CB6E381AEE5AD90.jpg)