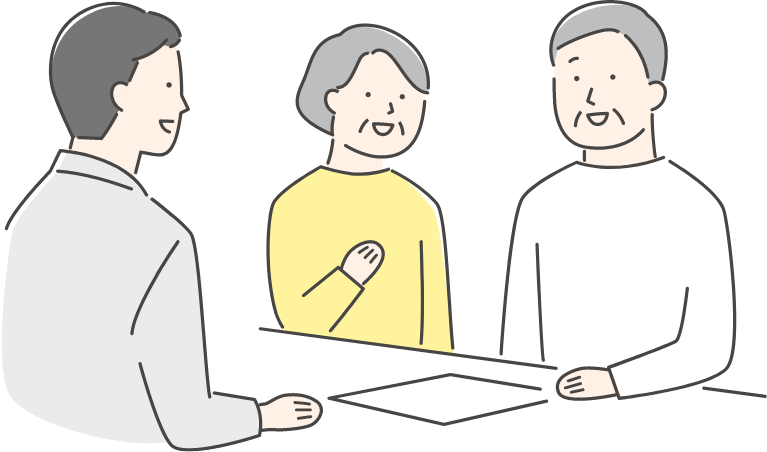
1分ですぐわかる
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
Q1
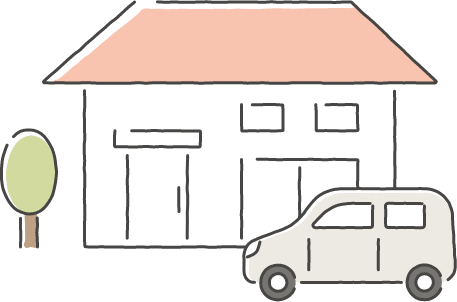
一軒家ですか?
Q2

4.5畳以上の部屋が
ありますか?
ありますか?
Q3
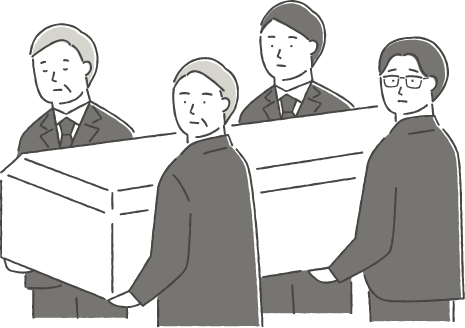
棺の出入りが可能ですか?
(棺サイズ:200cm×60cm)
(棺サイズ:200cm×60cm)
Q4
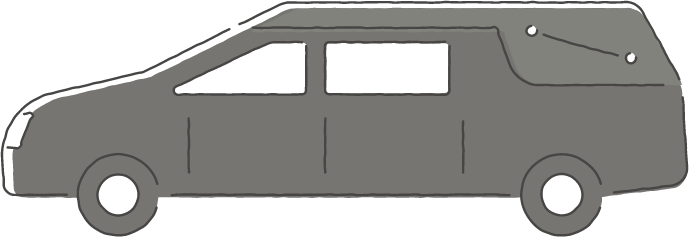
霊柩車が停められる
スペースがありますか?
スペースがありますか?
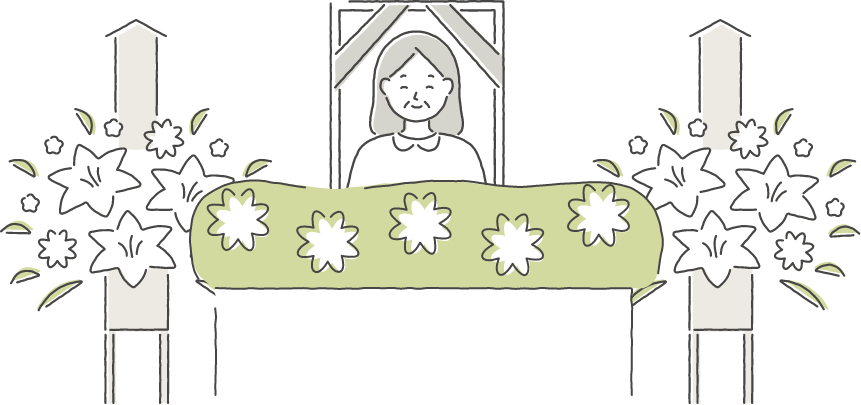
自宅葬が可能です。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

ご相談ください。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。









自宅という
特別な場所で
思い出を刻む
ひとときを。
自宅という特別な場所で
思い出を刻むひとときを。

慣れ親しんだ
自宅だからこそできる
「家族らしいお葬式」
慣れ親しんだ空間で、いつものように家族が集まり、大切な人を偲ぶ。自宅だからこそ叶う、温かな時間と心のこもったお見送りをお手伝いします。形式や宗教に縛られず、家族の想いを一番に考えたそれぞれの「家族らしいお葬式」で特別なひとときを過ごしませんか。
それぞれのご家族ごとの、自由なお葬式を

故人様が好きだった食事を持ち寄って、みんなで楽しむ。

好きな音楽を流し、故人様を想って祭壇を飾りつける手作りのお葬式。

大切な家族であるペットも、一緒にお葬式に参加できる。
自宅葬のサトリエが提案する
新しいお葬式の形

自宅葬のサトリエは、住み慣れた自宅から故人様をお送りする新しい形の葬儀を提供しています。たくさんの思い出が詰まった世界に一つのご自宅で、最後の旅立ちを提供したい。そんな想いを持ってご家族様と葬儀を作り上げていきます。
わかりやすい
料金体系

ご家族様の
想いを形に

葬儀後も
サポート


基本プラン29.8万円。
明確な料金プランで、
安心してご利用いただけます。
自宅葬のサトリエでは、花飾りや棺の種類によって4つの料金プランをご用意しています。明瞭でわかりやすい料金体系ですので安心してお任せいただけます。

FLOW自宅葬の流れ




COLUMNお役立ち情報
2026年02月02日 15時26分
葬儀の豆知識
1.お布施は「葬儀の対価」ではない。まず押さえたい考え方
寺院と檀信徒(門信徒)の関係には、古くからの支え合いがあります。一般的に、檀信徒(門信徒)に不幸があれば寺院が葬儀や仏事を勤め、檀信徒(門信徒)は寺院を護持し、お寺の営みを支える——そうした相互の関係の上に成り立ってきました。昔のお葬式は、今とは少し形が違いました。香典をはじめ、ご近所・組内・親族の協力によって葬儀が成り立ち、当家が負担する費用は、現在ほど大きくないケースも多かったと言われます。だからこそ、葬儀の節目で寺院へ「お布施」をお渡しすることが、自然で合理的な形でもありました。ここで大切なのは、お布施は「葬儀をしてもらった対価(料金)」ではないという点です。
お布施は僧侶への謝礼金ではなく、菩提寺の護持、仏様への“お供え”としての意味合いがあります。
2.「できる範囲で良い」けれど、「安くすれば良い」ではない
お布施は、当家の経済状況に合わせて、無理のない範囲でよいものです。
一方で、「できるだけ安く済ませたい」という発想だけで決めてしまうと、寺院との関係性や、護持本来の目的が失われてしまいます。
大切なのは、できる範囲をきちんと考えたうえで、寺院と相談して決めること。
これは決して失礼なことではなく、むしろ「失礼のないようにしたい」という誠実な姿勢として受け止められることが多いです。
3.お布施で迷ったとき、寺院への相談は「丁寧に確認」がいちばん
もしお布施に迷う場合は、次のように尋ねると角が立ちにくく、話がスムーズになります。
「失礼があってはいけませんので、お布施はどの程度お包みするのがよろしいでしょうか?」
「経済的に〇〇万円程度が精一杯ですが、よろしいですか?」
「院号はいかほど、お包すればよろしいですか?」
4.お布施のおおまかな種類
≪種 類≫
御布施(葬儀)
御布施(通夜)
御布施(枕経)※真宗は臨終勤行
戒名冥加金※真宗の場合戒名はありません。
院号冥加金
御車代
御膳料
※上記お布施の種類は一例ですので、寺院へ直接ご相談いただくようお願い致します。5.お布施の水引は何色が良いの?
お布施は白黒色の水引を使われる方が多いですが、お布施=不祝儀ではありません。
その為、水引の色は白黄か双銀の熨斗でもかまいません。
ただし、結婚式で使うような派手な物は避けて、一般的なのし袋を使用しましょう。6.お布施を渡すタイミングやマナーは
お布施を渡されるタイミングはいつでもかまいませんが、式の差し支えが無い時にお渡ししましょう。
例えば:葬儀開式前・出棺前・火葬後・お礼山
またお渡しするマナーとして袱紗(ふくさ)や切手盆からお渡しする方が良いでしょう。
7.まとめ
お布施はどうしたらいいの?という疑問はお葬式を行う方にとって悩まれる事の一つですが、分からない事は失礼だと思わずに寺院へ相談しましょう。サトリエへご相談される方におかれましても丁寧にご返答させて頂きますので、ご遠慮なくご相談下さい。
2026年02月02日 11時12分
お葬式の費用
葬儀の豆知識
「家族葬と直葬って、何が違うの?」とうい意見を稀にうかがう事があります。
お葬式は一家にとってめったにある事ではありませんので、事前知識が無いと、いざお葬式の場面になった時に困りますよね。
本日は家族葬と直葬の違いや、選ぶ時の注意点をご説明させて頂きます。1.家族葬と直葬は何が違う?
家族葬と直葬との大きな違いとして「宗教家」による儀式を行うかです。
実は家族葬は一般的なお葬式の流れと変わりません。
家族葬とはその名の通り「家族中心のお葬式」という意味ですので、何かを省略したりする事もありません。
一方直葬とは「宗教家による儀式を行わないお葬式」です。
直葬と似たカタチのお葬式では「お別れ会」であったり、「火葬式」と言ったりもします。
仏教のお葬式では通常 安置→枕経→通夜→葬儀→お別れ→火葬→法要 という流れですが、直葬の場合は、安置→お別れ→火葬のみになります。
家 族 葬
直 葬
安 置
自宅or葬儀場
自宅or葬儀場
枕 経
〇
×
通 夜
〇
×
葬 儀
〇
×
お別れ
〇
〇
火 葬
〇
〇
法 要
〇
×
病院から直接火葬場へ行くと思われている方もいらっしゃいますが、火葬の法律で、原則24時間以内の火葬は禁じられています。つまり、一時的に24時間安置できる場所が必要となります。
2.葬儀費用はどう違う?
さて、家族葬と直葬の違いは説明しましたが、かかる費用負担はどう違うのでしょうか?
家族葬は人数制限による会葬礼品や食事などの費用を抑える事により、葬儀費用全体を低く抑える事が可能です。
お葬式では一般的に必要な物として、棺や骨壺、車両や祭壇、会館使用料金、お布施などが必要となります。
家族葬でも、儀式を行う場が必要となりますので、最低限必要な費用はかかります。
一方直葬は、祭壇や会館使用料、お布施は、不要なケースが多く(遺体安置は利用する場合はある)家族葬に比べると、費用負担は少なく抑えられます。
品 目
家族葬
直 葬
祭 壇
必 要
不 要
会場費
必 要
不 要
棺・骨壺・ドライアイス
必 要
不 要
生 花
必 要
任 意
霊柩車などの車両
必 要
必 要
料理・会葬礼品
任 意
任 意
遺影写真
任 意
任 意
遺体安置室
任 意
必 要
お布施
必 要
不 要
【一般的な葬儀費用】
家族葬 … 60万円~120万円
直 葬 … 20万円~40万円
※上記の費用は一般的な目安です。葬儀社により多少前後します。
3.家族葬や直葬の特徴や注意点
【家族葬の特徴】
家族葬の特徴は一般葬と比べ、費用を抑えられる事が多い点と、家族中心でお葬式を行う分、プライベート空間を保ちやすいという点です。
特に核家族化や地域住民とのご関係が希薄になった現代だからこそ、受け入れやすい葬儀スタイルだと言えます。
また、近年のお葬式の大半がこの家族葬を選ばれています。【家族葬の注意点】
家族葬の注意点は参列者を制限する分、葬儀後にご自宅へ弔問される方が増える点です。また、弔問出来なかった方から「弔問したかった」「どうして教えてくれなかったの」というトラブルも…【対 策】
回覧板やSNSでお知らせだけはしっかりと行う。
通夜だけ弔問に来ていただく。
開式前の事前焼香・お別れの時間を設ける。
参列して欲しい方が多いようなら一般葬へ変更する
【直葬の特徴】
直葬の一番の特徴は費用を抑えられる点です。一般葬や家族葬と違い、葬儀式を行わない分、費用負担は少ないと言えます。
また、打合せでの決め事も少ないので、時間的負担も少なくて済みます。【直葬の注意点】
葬儀式をしない分、火葬後の後悔がおきやすいお葬式スタイルでもあります。お葬式はご逝去から2日~4日程度で行いますので、どうしても急いで決めないといけない事が多くあります。費用だけで決めてしまって、弔いの場を設けれず、小さくてもお葬式をすればよかったという声を聞く事もあります。
また菩提寺がいらっしゃる場合、寺院との今後の関係に困る事もあります。【対 策】
まず一人で考えるのではなく家族やご親族と話し合う。
予算の範囲でできる事を知る。
葬儀会社の担当者としっかりと相談をする。
4.自宅でもお葬式は可能
家族葬や直葬のどちらを選ばれたとしても、最低限の費用が必要となります。費用負担として大きいのが「会館の使用料」です。
会館を使用するだけでも、10万円前後の費用が必要となる場合がありますが、少人数であれば、皆様のご自宅でもご遺体の安置やお葬式は可能です。またご自宅であれば、常に故人に付き添い、お別れの時間を設ける事が可能ですので、費用面と気持ちの部分の両方にとってメリットがあります。
また家族葬を選ばれる方には「お寺でお葬式」もオススメ致します。
お寺で行うお葬式は「寺院葬」ともいい、お寺の本堂や檀信徒会館で通夜から葬儀、法要まで行うお葬式です。
主な特徴として、会場費が安い、祭壇がいらないという点です。お寺は檀信徒の方の共有財産です。
また費用だけでなく、住職との距離も近い分、法要やお墓の相談までしやすいという点も魅力的です。
5.まとめ
お葬式は一度行えばやり直しは出来ません。その分一番最初の判断が重要です。家族葬や直葬にしても、大切な方との最期のお別れに代わりはありませんが、それが後悔するものであってはいけません。
お葬式を行う方にとって、本記事が少しでも役立てて頂ければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
2026年01月26日 15時50分
葬儀の豆知識
家族葬を考えるときに一番悩みやすいのが、「誰まで参列してもらうか(誰に声をかけるか)」です。呼ばなかったことで後から気まずくなったり、逆に呼びすぎて“家族葬のはずが一般葬みたいになった”というケースもあります。この記事では、家族葬の参列範囲の決め方と、トラブルを防ぐコツを分かりやすく整理します。
そもそも家族葬の「参列範囲」に決まりはない
家族葬は「参列者を近親者中心に絞って行う葬儀」の総称で、人数の明確なルールがあるわけではありません。
一般的には 数人〜30名程度 の規模が多く、家族親族+特に親しい人 を中心に行われます。
よくある参列範囲のパターン
迷ったら、次の3つの段階に分けて考えると整理しやすいです。① 最小限(本当に近い家族だけ)
こんな時に向く
高齢で参列者対応が難しい/静かに見送りたい/参列を極力少なくしたい
配偶者、子、同居家族
必要に応じて:故人の親、兄弟姉妹
② 標準(親族まで)
①+兄弟姉妹の家族
①+おじ・おば、いとこ(近い関係なら)
近所や親しい友人を数名だけ
こんな時に向く
家族葬らしさを保ちつつ、親族の理解も得やすいバランス型
③ 広め(親族+親しい関係者)
②+故人と交流の深かった友人
②+会社関係(直属の上司・同僚など少人数)
②+お世話になった方(恩人、地域のつながり等)
こんな時に向く
「お別れしたい人」が一定数いる/後悔を減らしたい/弔問を後日に分散させたくない
参列範囲を決める“現実的な基準”5つ
「気持ち」だけで決めると揉めやすいので、次の基準で整理すると失敗が減ります。
故人が生前よく会っていた人か
喪主(遺族)が対応できる人数か(挨拶・焼香案内・会計など)
会場の広さ・導線(自宅・寺院・ホールで収容が変わる)
香典を受ける/受けない(香典辞退なら参列も絞る方が整合しやすい)
後日の弔問が増えても大丈夫か(家族葬は「あとから来客が続く」ことも多い)
トラブルになりやすいポイントと対策
「呼ばれなかった」と言われる
対策:参列を絞るなら、事前に説明を用意します。
「家族だけで静かに見送ることにしました」
「体力面を考えて近親者のみで執り行います」
「落ち着いたら改めてご挨拶させてください」
参列を絞ったのに、情報が広まって人が来る
対策:訃報連絡の範囲を最初に決めて、伝え方を統一します。
LINEなどを活用して訃報をお知らせする場合、文章を工夫する事が大切です。
家族葬にしたら、後日弔問が続いて大変
対策:最初から「弔問対応の窓口」を決める。または「弔問はご遠慮ください」と明確にすると負担が軽くなります。
「声をかける人」と「知らせる人」を分けると上手くいく家族葬は、次の2種類に分けて考えると整理がつきます。
参列してもらう人(声をかける)
参列はしないが、後で訃報だけ伝える人(知らせる)
たとえば会社関係は「参列は辞退いただき、後日訃報のみ」にすると、角が立ちにくい場合があります。まとめ:迷ったら“後悔が少ない範囲”を基準に参列範囲に正解はありません。ただし、家族葬は「少人数で心を込めて見送る」良さがある一方で、呼ぶ・呼ばないの判断が人間関係に影響しやすい葬儀でもあります。迷ったら、
故人が会いたかった人
遺族が無理なく対応できる人数
後日の弔問負担も含めた全体最適
この3つで決めるのがおすすめです。
2026年01月08日 18時57分
お知らせ
令和8年1月7日、福山市御船町の真宗大谷派・淨願寺様のご本堂にて、第15世坊守様の寺院葬を執り行いました。葬儀施行は、寺院・自宅葬のサトリエが担当いたしました。
坊守様は令和8年1月4日(日)にご逝去され、1月6日に通夜、1月7日に葬儀を勤修する運びとなりました。中国新聞のお悔やみ情報への掲載も行い、門徒の皆様、近隣寺院の皆様、そして関係各位へ広くご案内する中で、当日は寺族・親族・一般のご参列者・門徒の皆様と、多数の方々にお集まりいただきました。あらためて、深いご縁とお心添えに感謝申し上げます。
本葬儀は、淨願寺様の門徒の皆様ならびに近隣寺院の皆様のご協力のもと、ご本堂という厳かな空間で、真宗大谷派のご作法に則り滞りなく執り行われました。導師は真宗大谷派・明真寺様にお勤めいただき、僧侶方のご助力、門徒の皆様の支えにより、坊守様をお見送りするにふさわしいご葬儀となりました。
また、出棺に際しては、最期の霊柩車として、昨今では珍しい宮型霊柩車にて福山市中央斎場までお送りいたしました。地域の記憶に残る形式でお見送りできたことは、坊守様が大切にされてきたご縁や歩みを、皆様と共に改めて確かめるひとときにもなったように感じております。
サトリエでは、「会館ありき」ではなく、故人様とご家族の想いに合わせて、寺院・ご自宅など最適な場所から葬儀を組み立てることを大切にしています。今回のように、寺院様・門徒の皆様・地域の皆様と力を合わせて執り行う寺院葬は、宗門のご縁を確かめ、故人様の歩みを丁寧に受けとめる時間になります。坊守様のご往生を謹んでお悔やみ申し上げるとともに、これまで賜りましたご厚情に深く御礼申し上げます。
2025年12月13日 16時30分
お葬式のマナー
お葬式の焼香について知ろうお葬式で行われる焼香は、日本の葬儀において重要な儀式の一つです。初心者の方にとっては、その意味や作法がよくわからないということもあるかもしれません。この記事では、焼香の目的やその作法について詳しく解説します。焼香の目的とは?焼香とは、香を焚く行為のことで、主に仏教のお葬式で行われます。焼香には以下のような目的があります。
仏様へ焼香の香りをお供える事
故人を偲び、感謝する時間
焼香をすることで、故人への尊敬と感謝を表現することにもなります。
焼香の作法焼香には、立礼焼香、座礼焼香、回し焼香の三種類があります。それぞれの作法についてご説明します。立礼焼香立ったまま焼香台の前に行く方法です。最も一般的に行われる焼香方法で、以下の手順で行います。
一礼:焼香台へ進む前に遺族に対して一礼をします。その後、ご尊前に対して一礼します。
香を取る:右手の親指・人差し指・中指で香を取り、左手で軽く支えます。
香を焚く:香を一度、または複数回焚きます。※宗派によって異なります。
一礼:香を焚き終えた後、遺族に向かって一礼します。
座礼焼香畳の部屋などで、座った状態で行う焼香です。基本的な流れは立礼焼香と同様ですが、座り方や体の向きに注意が必要です。座礼のポイント:正座し、焼香台に向かってゆっくりと進みます。焼香を終えたら、最後にもう一度正座に戻ります。回し焼香椅子に座った状態で、焼香具が順に回ってくる形で行う焼香です。主に多数の人がいる葬儀や法要で使われます。各自の注意:焼香具が回ってきたら、立礼焼香と同様の手順で焼香を行い、次の人に丁寧に回します。
焼香の回数や方法は、宗派によって異なる場合があります。参加する葬儀社のスタッフに確認すると良いでしょう。
焼香の作法
焼香の回数は宗派によって異なります。
福山市の主な宗派の焼香回数をご紹介致します。
各宗派の焼香回数と作法
浄土真宗本願寺派… 1回 額に押し頂かない
真宗大谷派 … 2回 1度目は額に押し頂き2度目は静かに供える。
真言宗 … 3回 3度とも額に押し頂く
浄土宗 … 回数に決まり無し
曹洞宗 … 2回 1度目は額に押し頂き2度目は静かに供える。
日蓮宗 … 3回 3度とも額に押し頂く
作法はそんなに気にしなくても
焼香で大事な事は、作法よりも故人を偲び、仏様へ感謝する気持ちです。焼香後には皆様合掌を行いますが、合掌し、故人様への想いを心の中で感じて頂く時間にこそ、焼香本来の意義があります。お葬式の作法や仏事についても、いつでもご相談承ります。
24時間365日対応しておりますので、ご遠慮なくご相談下さい。
自宅葬のサトリエ
☎084-999-0512
福山市瀬戸町山北458‐1
2025年12月09日 21時27分
葬儀の手続き
「うちはお寺とのお付合いがないけど、お葬式ってどうしたらいいの?」実はこのご相談、とても多いです。核家族化や引っ越しの増加で、“菩提寺(先祖代々のお寺)を持たないご家庭” は年々増えています。でも、お寺とのお付合いがないからといって、慌てる必要はありません。きちんとお別れをする方法はいくつもあります。この記事では、「お葬式、お付合いのお寺がいない場合はどうしたらいい?」という不安にお応えしながら、具体的な選択肢や考え方をわかりやすくまとめました。1.まず知っておきたいこと「お寺がない=お葬式ができない」ではない
「お寺がないとお葬式ができない」と思っておられる方は多いですが、実際には以下のようなパターンがあります。
葬儀社からお寺(僧侶)を紹介してもらう
自分で近隣のお寺に依頼する
無宗教形式の葬儀を行う
火葬式のみで見送る(お経や読経はなし)
つまり、お寺とのお付合いがないからといって、お葬式自体ができないわけではありません。「どんな形で見送りたいか」を決めるところから始めれば大丈夫です。2.まずは葬儀社に相談するのが安心身内が亡くなった直後は、気持ちも動揺し、冷静に考えるのが難しいもの。「どのお寺に頼めばいいのか」「宗派はどうしたら…」と、一つひとつ自分たちで探すのは大きな負担です。そこでおすすめなのが、まず葬儀社に相談することです。葬儀社にはこんな相談ができます。
「お付合いのお寺がないのですが、お葬式はできますか?」
「宗派は特にこだわりがないのですが、どうしたらいいですか?」
「菩提寺らしいお寺が昔あったかもしれませんが、わからないです」
多くの葬儀社は、提携しているお寺・僧侶 がいます。宗派の希望を聞いたうえで、読経や戒名(法名)をお願いできるお寺を紹介してくれます。
ポイント:
「お布施の目安はいくらくらいですか?」
「葬儀後の法要などもお願い出来ますか?」
「納骨堂などのご相談も可能ですか?」
なども、遠慮なく事前に確認しておきましょう。
3.菩提寺がない場合の「お寺の選び方」「せっかくなら、今後もお付き合いできるお寺を探したい」という方もおられます。その場合、次のような点を意識してお寺を選ぶと安心です。① 通いやすさ・立地
自宅やお墓から通いやすい場所か
高齢になってからも無理なく足を運べる距離か
② お寺の雰囲気・住職との相性
話を丁寧に聞いてくれるか
専門用語ばかりでなく、わかりやすく説明してくれるか
ご家族の事情(家族葬や小規模葬など)を理解してくれるか
③ 費用や今後のお付合いについて
お布施の目安を教えてもらえるか
法事や年忌のお参りのスタイル・頻度はどうか
檀家になる場合の条件や費用はどうか
一度お話を聞きに行き、「このお寺なら相談しやすい」と感じられるかどうかは、とても大切なポイントです。4.宗派がわからない・こだわりがない場合「ご先祖の宗派がわからない」「特に宗派にこだわりはない」というケースも珍しくありません。その場合の考え方としては…
葬儀社に相談し、一般的によく選ばれている宗派・お寺を紹介してもらう
今後、自分たちがお付き合いしていきたい宗派を選び、そのお寺にお願いする
宗教色の強くない、シンプルな葬儀(読経あり・戒名なし、など)を相談する
大切なのは、**「故人と家族が納得できるかどうか」**です。形式に縛られすぎず、「この形なら心から送り出せる」と感じられる方法を選びましょう。5.お布施・費用面で気をつけたいことお寺とのお付合いがない方にとって、一番不安なのが「お布施はいくら必要?」という点かもしれません。事前に必ず確認しておきたいこと
お布施の「目安金額」を聞いておく
戒名(法名)の有無や、その際の費用の目安
お車代・御膳料(会食がない場合)の扱い
葬儀後の法要(四十九日、初盆、一周忌など)をお願いする場合の費用感
金額は地域やお寺によって幅がありますが、「相場がわからないまま、あとで驚く」 という事態は避けたいところ。葬儀社かお寺のどちらかに、勇気を出して事前確認しておくのがおすすめです。6.無宗教葬という選択肢もある「宗教色をあまり出したくない」「読経や戒名よりも、故人の音楽や思い出を中心に送りたい」そんな場合は、無宗教葬(自由葬) という形も選べます。無宗教葬の特徴は…
お経や読経が必須ではない
音楽や映像、手紙の朗読など、自由な構成ができる
宗派やお寺とのお付合いにとらわれない
一方で、
後々「やはりお墓や供養のことを考えると、お寺とのつながりも持っておけばよかった」と感じる方もおられます。
無宗教葬を選ぶ場合も、「その後の供養をどうしていきたいか」 という視点を持っておくと安心です。7.できれば「事前相談」がおすすめ身内が亡くなってから、短い時間の中でお葬式の形式・葬儀社・お寺・費用…すべてを決めるのは、本当に大変です。お寺とのお付合いがないご家庭こそ、「もしもの時のために、事前に相談しておく」 ことをおすすめします。事前相談でわかること
自分たちに合ったお葬式の規模や形式
地域の相場感(葬儀費用・お布施)
お寺の紹介の有無・費用
自宅葬・家族葬・火葬式など、それぞれの違い
相談したからといって、必ずそこに依頼しなければならないわけではありません。まずは情報を知ることが、いざという時に慌てない一番の備えになります。8.まとめ:お寺がなくても、納得のいくお別れはできる
お付合いのお寺がなくても、お葬式はできます
まずは葬儀社に相談し、お寺や葬儀の形式を一緒に考えてもらいましょう
菩提寺がない場合は、「通いやすさ」「住職との相性」「費用」を意識してお寺を選ぶ
宗派にこだわりがない場合や、無宗教葬という選択肢もあります
お布施や今後の法要については、必ず事前に目安を確認する
できれば、元気なうちに事前相談をしておくと安心
「お寺がないからどうしよう…」という不安を、一人で抱え込む必要はありません。わからないことは、葬儀の専門家に相談して大丈夫です。ご家族らしい形で、大切な人をきちんと送り出すために。早めに情報を知り、少しずつ「わが家のお葬式」をイメージしてみてください。












