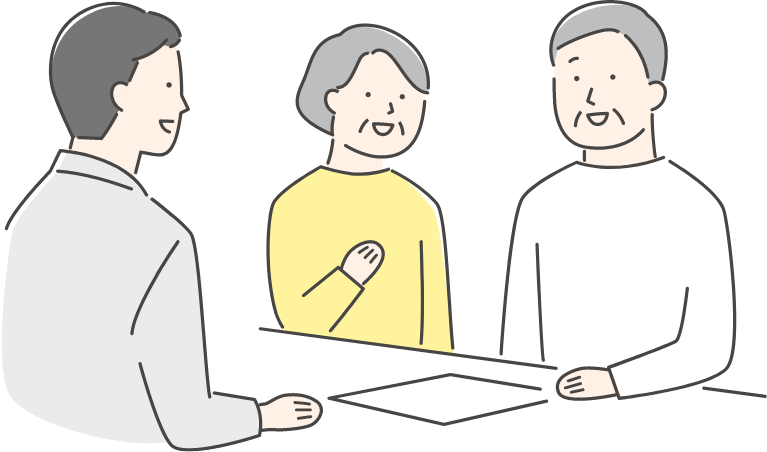
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
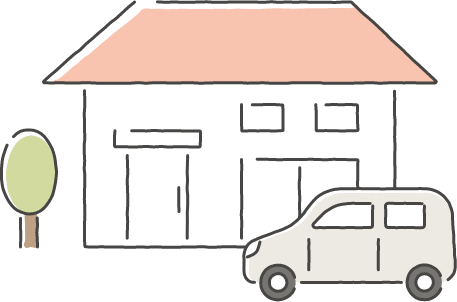

ありますか?
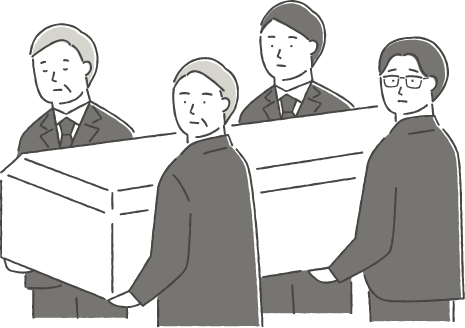
(棺サイズ:200cm×60cm)
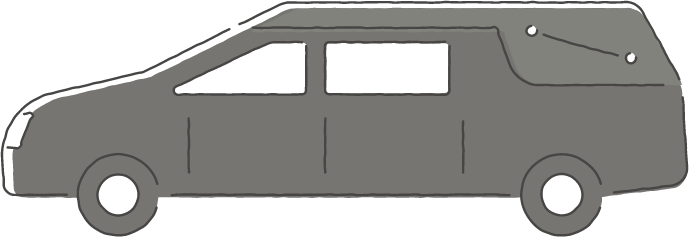
スペースがありますか?
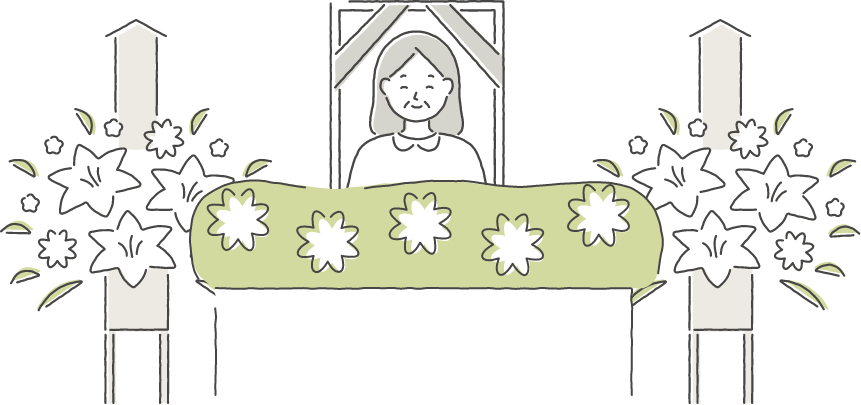
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
お葬式のとき、神棚封じは必要?意味と正しいやり方を解説
2025年05月16日身近な方のお葬式があるとき、「神棚封じってした方がいいの?」と迷ったことはありませんか?
仏式の葬儀でも、神棚のあるご家庭は多く、どう対応すべきか分からない方も多いと思います。
今回は、神棚封じの意味や正しい方法、そしてどんな場合に行うのかをわかりやすく解説します。
そもそも「神棚封じ」とは?
神棚封じとは、神棚の扉を閉じて白い半紙などで覆い、死を“けがれ”として神様から遠ざけるための風習です。
神道では、「死」は穢れ(けがれ)とされ、神様の領域とは別に扱うべきものとされています。そのため、忌中の間は神棚を封じて、神様に影響が及ばないようにします。
神棚封じはいつ、誰がするの?
基本的には、亡くなった方と同じ家に神棚がある場合に行います。
● 神棚封じをするタイミング:
- ご家族が亡くなった直後(できるだけ早め)
- 遺体を自宅に安置する前までに済ませておくのが一般的
● 封じる人:
- 通常はご家族が行いますが、葬儀社に相談すれば対応してくれる場合もあります。
神棚封じのやり方
やり方はとてもシンプルです。
- 神棚の扉を閉じる(開いている場合)
- 半紙や白い和紙を使って、神棚全体を覆う
- 忌明け(四十九日または五十日祭)まで封じたままにしておく
※紙は四角く切ったものをテープなどで軽く貼るだけでOK。
※完全に布などで隠す地域もあります(地域差あり)。
神棚封じは仏式でも必要?
仏教葬儀が多い現代でも、神棚があるなら封じておくのが一般的なマナーとされています。
たとえ仏式であっても、「神道の要素が家庭にある場合は、それに沿った習わしを大切にする」という考えが根強いです。
忌明け後の神棚開き
神棚封じは「忌中」の間続けます。
仏式であれば四十九日、神道であれば**五十日祭(仏教の四十九日に相当)**が終わったタイミングで、封じた半紙を外します。
※手を清め、軽く礼をしてから封を解くのが一般的です。
【豆知識】神棚がない場合はどうする?
近年は神棚がないご家庭も多いため、封じ自体を行わないケースもあります。
ただ、実家に神棚がある場合などは、帰省の際に気をつけると良いでしょう。
サトリエからひとこと
仏教葬を中心にサポートするサトリエでは、宗派や地域のしきたりに合わせた対応もご相談いただけます。
「うちは神棚あるけど、どうすれば?」
「お寺葬で神棚って関係あるの?」
そんな疑問にも、経験豊富なスタッフとお寺の視点から丁寧にご案内いたします。
▶︎ ご相談はいつでも無料です。[サトリエ公式サイト]自宅葬のサトリエ|福山市を中心に備後エリアで自宅葬なら
まとめ:神棚封じは「伝統と敬意」の表れ
神棚封じは、「神様に対する敬意」と「心を整えるためのけじめ」として続けられてきた習わしです。
無理に行う必要はありませんが、意味を知って丁寧に向き合うことが、故人を大切に思う心につながります。
わからないことがあれば、一人で悩まず、ぜひ専門家に相談してみてくださいね。








