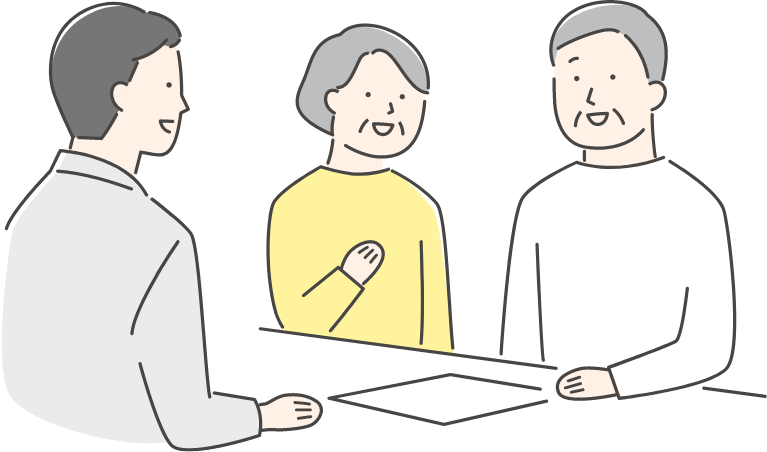
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
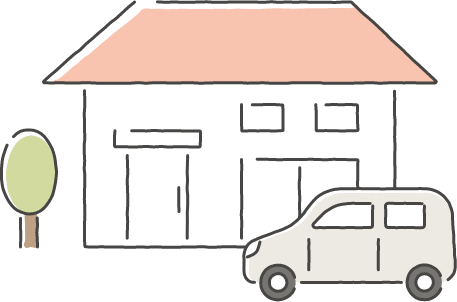

ありますか?
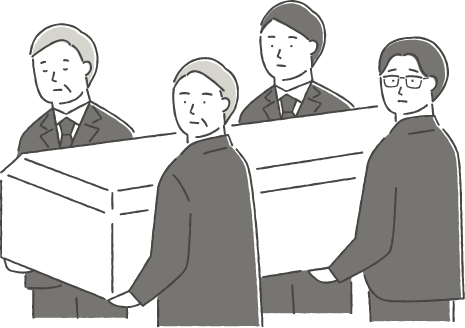
(棺サイズ:200cm×60cm)
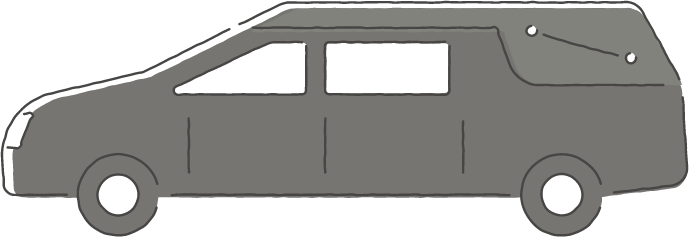
スペースがありますか?
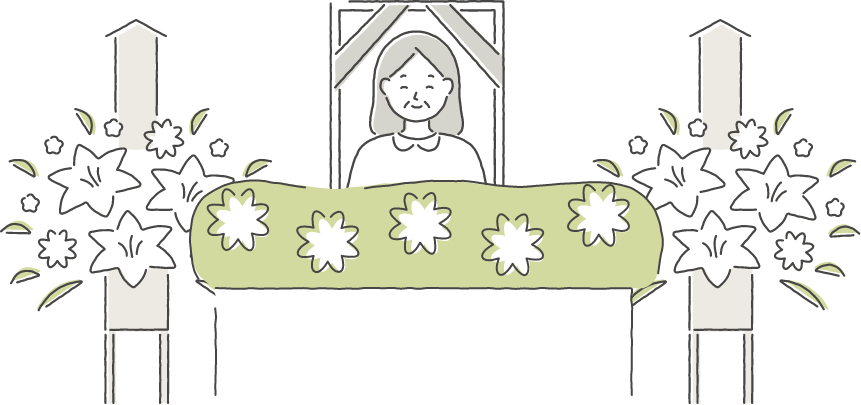
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
四華花(しかばな)とは?葬儀に添えられる白い紙花の意味
2025年05月18日葬儀やお通夜に参列したとき、白い紙で作られた独特な花を見かけたことはありませんか?
それは「四華花(しかばな)」と呼ばれる、仏教葬における特別な意味を持つ花です。
今回はこの四華花について、その意味・由来・飾り方などをわかりやすく解説します。
■ 四華花とは?
四華花(しかばな)とは、主に仏教の葬儀で使われる、白い紙で作られた造花のこと。
地域によっては「紙花(かみばな)」「四花(しか)」とも呼ばれます。
多くの場合、以下のような場面で見かけます:
- 枕飾り(故人の枕元)に立てる
- 棺のまわりや祭壇に添える
- 葬儀や通夜のときの飾りとして使用
- お墓に立てる
■ 四華花の意味と由来
「四華」とは、仏教で言う四種の美しい花を指しています。
- 蓮(ハス)
- 優曇華(うどんげ)
- 摩訶曼陀羅華(まかまんだらけ)
- 摩訶沙羅華(まかしゃらけ)
これらの花は、仏の世界(極楽浄土)に咲く神聖な花として信じられており、葬儀で使用することで「故人が極楽浄土に導かれるように」という願いが込められています。
現代では、生花ではなく白い紙で簡略的に表現されるのが一般的です。
■ なぜ白いのか?
四華花の起源は、お釈迦様が入滅(にゅうめつ)された時に由来します。
お釈迦様がお亡くなりになられたときに周囲の沙羅双樹(さらそうじゅ)が白い花を咲かせたという事に由来します。
こうした背景から仏教では葬儀にはこの沙羅双樹を模した花(四華花)を飾るようになったと言われております。
■ 四華花の飾り方・扱い方
多くの場合、以下のように使われます:
- 枕飾りの左右に1本ずつ立てる
- 枕飾りや祭壇に並べて供える
- 地域によっては火葬のときに棺に一緒に納める
飾る場所や数は宗派や地域によって異なるため、葬儀社や寺院に確認すると安心です。
■ 四華花はどこで手に入る?
四華花は、葬儀社が準備することが多いため、自分で用意することはほとんどありません。
ただし、手作りされる地域もあり、家庭で折って作ることもできます。
■ サトリエでは、四華花を含めた丁寧な仏教葬をサポート
地域密着で仏教葬をサポートする**「サトリエ」**では、四華花の意味を大切にしながら、
枕飾りや祭壇の設営も仏式に則って丁寧に行っています。
「これって必要?」「宗派的にどうすれば?」
そんな細やかな疑問も、お寺との連携によって安心してご相談いただけます。
▶︎ 詳しくはこちら:[サトリエ公式サイト]自宅葬のサトリエ|福山市を中心に備後エリアで自宅葬なら
まとめ:四華花は、極楽へ導く“祈り”の象徴
四華花は、見た目はシンプルでも、
「故人が仏のもとへ導かれ、安らかに眠れるように」という深い祈りが込められた存在です。
現代ではあまり知られていないからこそ、その意味を知ることで、
葬儀の場に流れる“心”をより感じられるかもしれません。








