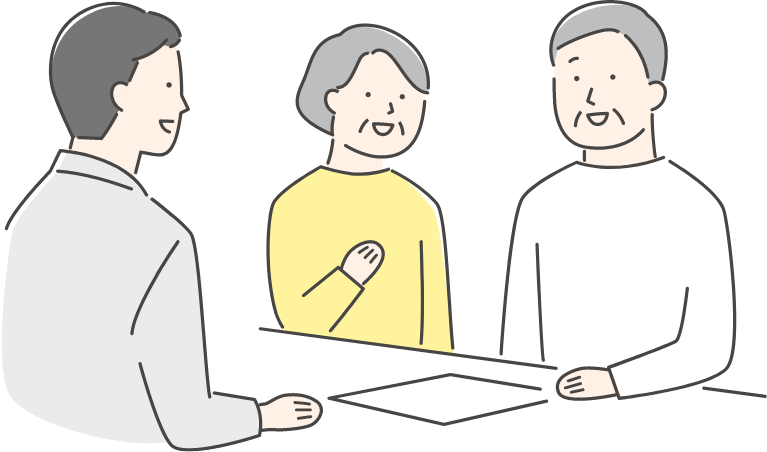
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
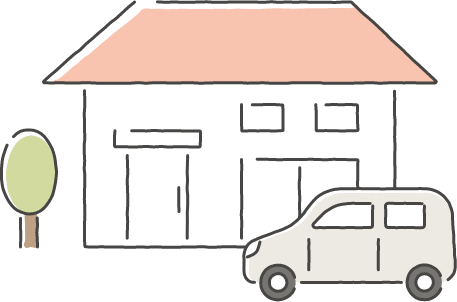

ありますか?
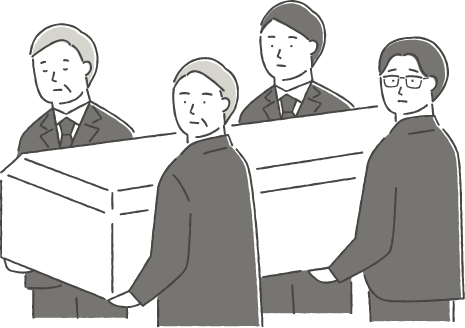
(棺サイズ:200cm×60cm)
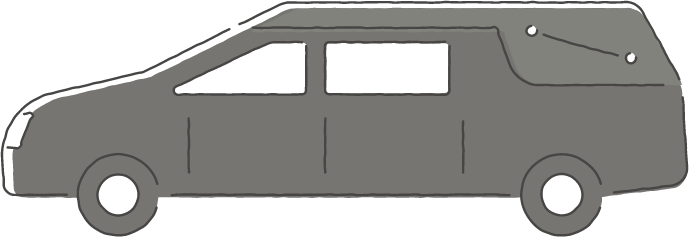
スペースがありますか?
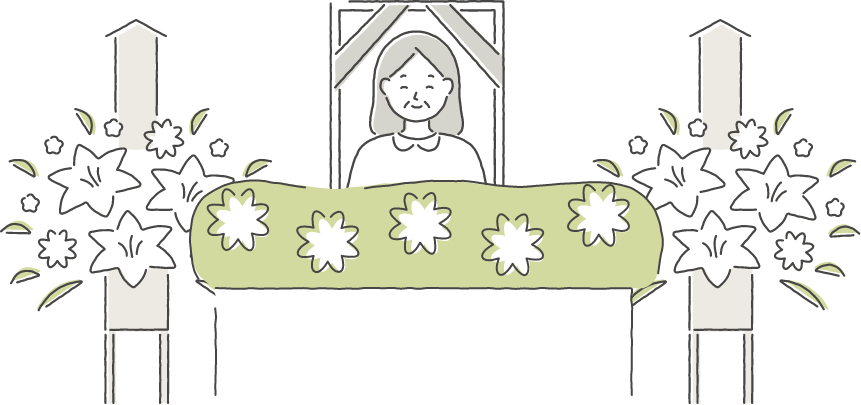
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
友引に葬儀をしてはダメ!? 〜友引の本当の意味と仏教における考え方〜[自宅葬のサトリエ]福山市・尾道市・府中市の葬儀
2025年06月28日「友引の日に葬儀は避けた方がいい」と聞いたことはありませんか?
実際に、火葬場が友引に休業している地域もあるほど、葬儀と友引の関係は一般にも広く浸透しています。
でも、本当に「友引=葬儀NG」なのでしょうか?
今回は、友引の本当の意味と、仏教における考え方について分かりやすく解説します。
友引とは何か?
友引(ともびき)は、「六曜(ろくよう)」と呼ばれる暦のひとつ。
もともとは中国の占いが由来で、日本では冠婚葬祭の日取りを決める際によく使われます。
六曜には以下の6つがあります:
- 先勝(せんしょう)
- 友引(ともびき)
- 先負(せんぷ)
- 仏滅(ぶつめつ)
- 大安(たいあん)
- 赤口(しゃっこう)
友引は「勝負ごとに勝つ」「友を引く」などとされ、午前・午後は吉、正午だけが凶とされています。
ここから、「友を引く=故人が友を道連れにする」と解釈され、葬儀を避けるべきとする風習が広まりました。
仏教の教えではどう考える?
実は、仏教には六曜の考え方は一切関係ありません。
六曜はあくまで俗信(世間の習わし)であり、仏教の教義や戒律に「友引の日に葬儀をしてはいけない」といった教えは存在しません。
ですので、仏教の立場からすれば、友引に葬儀をしても問題はないというのが正しい理解です。
なぜ友引を避ける風習が残っているの?
それでも友引を避ける風習が根強く残っているのは、主に以下の理由からです:
- 「縁起が悪い」と感じる方が多い
- 参列者に不安を与えたくない
- 火葬場が友引に休業する自治体が多いため
また、地域によっては「友引人形(ともびきにんぎょう)」を棺に入れる風習があり、これも「友引=道連れ」のイメージを強めてきました。
サトリエではご希望に応じた対応が可能です
「友引しか日程が合わないけど、心配…」
「家族だけの小さな葬儀だから、気にしなくてもいいかな?」
そんなご相談も、自宅葬・お寺葬のサトリエではよくいただきます。
私たちは、形式よりもご家族の想いや状況に寄り添ったお葬式を大切にしています。
友引であっても、希望があれば対応可能ですし、必要に応じてご遺体の安置や日程調整もサポートいたします。
まとめ
- 友引は暦の一種で、仏教とは関係ありません
- 葬儀を行ってはいけないという宗教的な理由はない
- 風習として避ける地域や人もいるため、配慮は必要
- 自分たちの気持ちを大切にしながら判断を
不安なことがあれば、どうぞお気軽にサトリエまでご相談ください。
お葬式は一度きりの大切な時間。誰よりも寄り添うサポートをお約束します。








