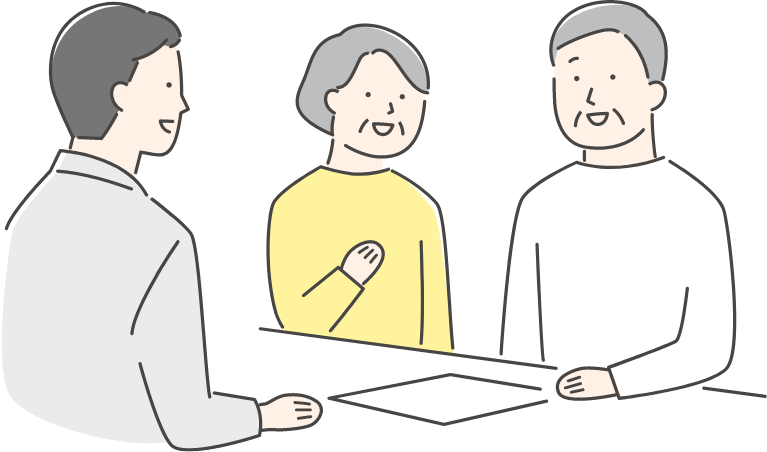
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
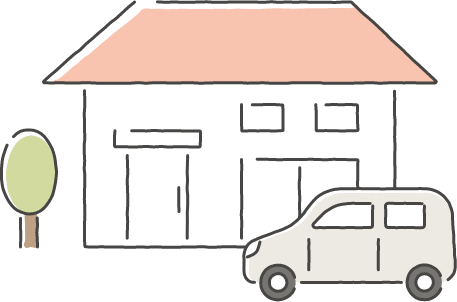

ありますか?
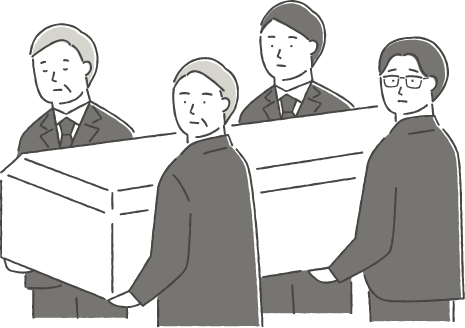
(棺サイズ:200cm×60cm)
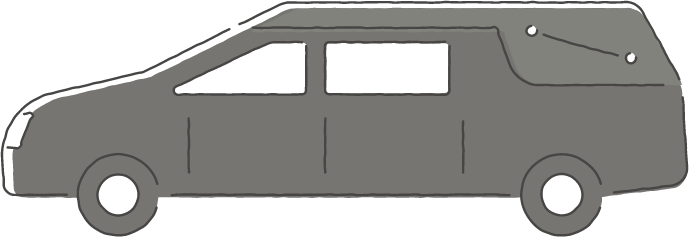
スペースがありますか?
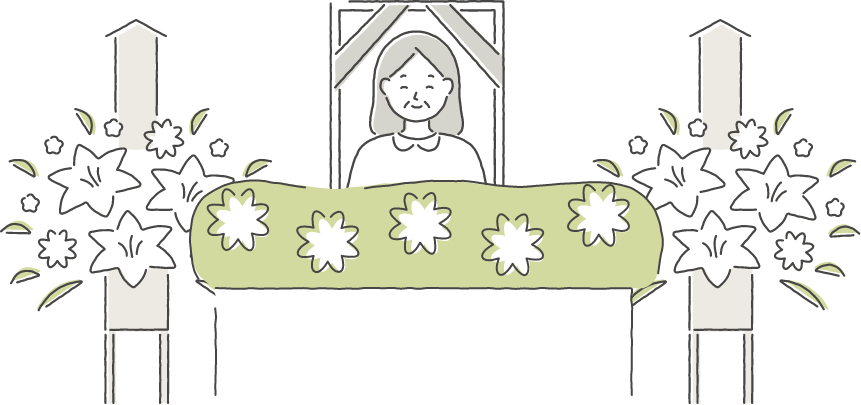
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
家族葬の招待範囲はどこまで?——迷わない決め方・伝え方・文例集
2025年08月18日1. 家族葬の“招待範囲”に正解はない——まず押さえる3つの軸
家族葬は参列者を絞る小規模葬。誰まで呼ぶかは家庭事情で異なります。迷ったら次の3軸で決めましょう。
- 故人の意思:遺言・生前の希望・宗教観
- 関係の濃さ:血縁(親等)だけでなく、生活上の支え・長年の交流
- 実務条件:会場定員・駐車台数・日程・予算・菩提寺の運用
ポイント:人数を“削る”発想ではなく、**「想いが届く最適人数」**を設計。
2. 目安にできる“親等”と例外の扱い
- 原則招待:1親等(配偶者・子・父母)+同居家族
- 状況により招待:2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)
- 原則は後日報告:3親等以降(伯叔父母・甥姪・曾祖父母 等)
- 例外:血縁より関係が濃い生前のキーパーソン(介護の担い手、長年の友人、地域の世話役 など)は招待候補に。
親族よりも深いお付き合いの友人がいる場合、親族A数名を外してまで友人Bを入れるより、後日の弔問機会を整える方が全体の納得感が高いことが多いです。
3. すぐ使える“招待範囲パターン”3選
◆ A. ミニマム(10〜15名)
- 1親等+同居家族
- 生前のキーパーソン1〜2名のみ
疲労や会場規模の制約が強いケースに。
◆ B. スタンダード(15〜30名)
- 1親等+2親等
- ごく親しい友人(各1〜2名)
- 町内会・自治会代表(1名程度)
“家族とごく近しい方”で静かに。
◆ C. 拡張(30〜50名)
- 1親等+2親等+3親等の一部
- 生前の交友(恩人・師・介護関係者)
寺院葬や広めの会場、駐車場確保が可能な場合。
4. カテゴリ別の判断基準
- 親族:疎遠・不仲・遠方・高齢等は負担も考慮。迷ったら**「喪主が直接連絡しケア」**を。
- 友人・知人:長年の交流/介護・通院同伴/日常的支援は招待有力。
- 近隣・町内:騒音・駐車配慮が要る自宅葬は代表者のみ参列、他は後日弔問に。
- 職場関係:部署代表や直属上司のみ参列、一般には参列辞退+ご報告が無難。
5. リスト作りの実務フロー(サンプル)
- A/B/Cランクに仕分け(A=必招、B=できれば招待、C=後日報告)
- 会場キャパ・駐車台数・受付人員から最大招待数を決定
- Bの中から優先基準(距離・支援度・家の合意)で人数調整
- 連絡文面を統一(電話/LINE/はがき/メール)
- 問い合わせ窓口を一本化(家族内の情報齟齬を防ぐ)
6. 伝え方の基本——案内・参列辞退・後日報告の“文言統一”
6-1 招待案内(家族葬・小規模/香典辞退可)
件名:ご葬儀のご案内(◯◯ ◯◯)
このたび◯◯◯(続柄・氏名)が永眠いたしました。
故人の希望により家族葬にて執り行います。
日時:◯月◯日(◯)◯時/場所:◯◯(駐車台数◯台)
なお誠に勝手ながら参列範囲を限らせていただいております。
香典・供花はご辞退申し上げます(お気持ちのみ頂戴いたします)。
お問い合わせ:喪主 ◯◯(電話:◯◯)
6-2 参列ご遠慮(丁重辞退)
このたびはご厚意ありがとうございます。
故人の遺志により近親者のみの家族葬といたしました。
まことに恐縮ですがご参列はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
後日あらためてご報告の機会を設けますので、その折はよろしくお願いいたします。
6-3 弔電・供花の受け方(辞退する場合)
お気遣いまことにありがとうございます。
家族葬の趣旨により弔電・供花も辞退いたしております。
温かいお言葉のみ頂戴できれば十分に存じます。
6-4 後日報告(はがき/LINE/SNS)
◯◯◯(氏名)は◯月◯日永眠いたしました。
葬儀は家族葬にて相済ませましたことをご報告申し上げます。
皆さまから賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。
なおお手を煩わせませんようご香典等は固くご辞退申し上げます。
生前のご厚誼に心より御礼申し上げます。
7. トラブルを防ぐ5つのコツ
家族会議で合意形成(「なぜ呼ばないか」理由も共有)
文言の統一(家族・寺院・葬儀社・職場で表現を揃える)
窓口を一本化(問い合わせ担当を1名決める)
後日の受け皿(弔問日・焼香時間・納骨時の案内など)
菩提寺と事前調整(読経・参列範囲・お布施・会場作法)
“呼ばれなかった”側の感情ケアとして、後日の弔問機会を明示すると不満の発生率が大きく下がります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1:疎遠な親族は呼ぶべき?
A:無理に呼ぶ必要はありません。配慮のある後日報告+弔問枠を案内しましょう。
Q2:職場はどこまで?
A:直属上司・同僚代表のみが無難。会社全体へは事後の社内告知で。
Q3:友人を呼びたいが人数が多くなる…
A:代表者1〜2名の“代理参列”や、お別れ会を後日設ける方法があります。
Q4:香典・供花は必ず辞退?
A:方針次第です。会食や返礼の負担を避けるなら一律辞退がシンプル。受ける場合は記帳とお返しの運用を事前に。
Q5:自宅葬でご近所は?
A:代表者のみ参列、他は弔問時間帯を後日設ける形が現実的。管理規約・駐車の配慮を。
9. 最終チェックリスト(当日3日前まで)
故人の意思と家族合意は一致している
招待上限人数・車両台数を確定
A/B/Cランクの境界に納得感がある
連絡文面・表現を統一(香典・供花の扱い明記)
問い合わせ窓口は一本化
菩提寺・会場と最終確認(読経・席次・焼香動線)
参列できない方向けの後日弔問の受け皿を準備
町内・管理組合への事前挨拶(自宅葬の場合)
当日受付の運用(芳名/記帳/返礼)を簡素化
事後のご報告テンプレ・宛先リストを用意
10. まとめ
家族葬の招待範囲は、**人数の多寡ではなく「想いが届く設計」**が本質です。
故人の意思・関係の濃さ・実務条件の3軸で判断し、文言統一と後日の受け皿で納得感を高めましょう。
事前相談・文面作成のサポート、寺院葬・自宅葬の設営や近隣配慮の段取りまで、サトリエが伴走します。福山市・尾道市・三原市・府中市を中心に備後地方の方はお気軽にご相談ください。








