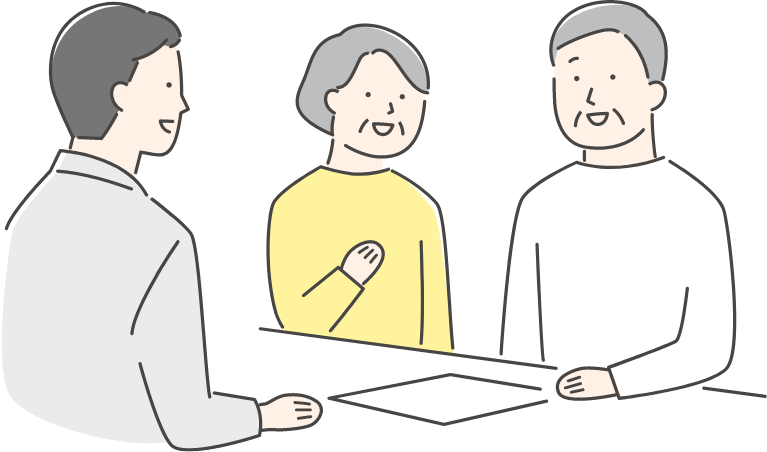
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
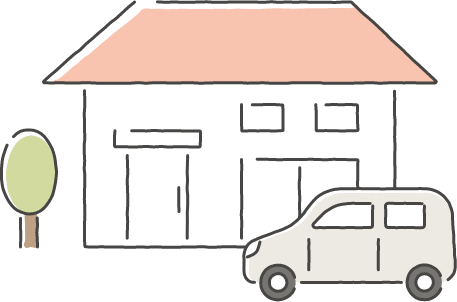

ありますか?
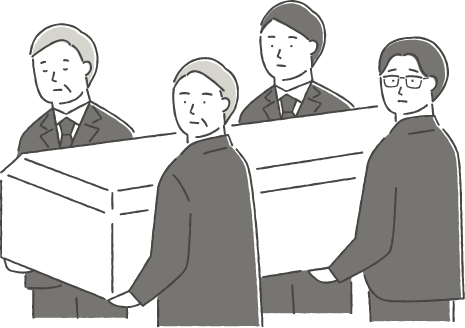
(棺サイズ:200cm×60cm)
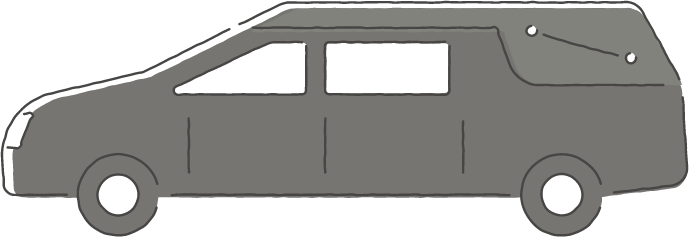
スペースがありますか?
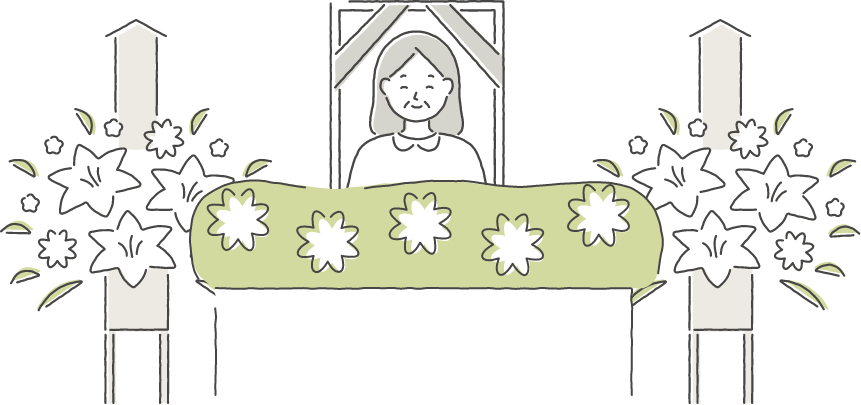
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
【福山市の葬送文化】昔のお葬式は“砂糖を付ける?”助け合いが生んだお葬式の文化
2025年08月28日福山市の昔ながらのお葬式には、「砂糖を付ける」という独特の風習がありました。砂糖には、地域の助け合い(組内・講組)からなるお葬式の文化と深く結びついていました。本記事では、その具体的なやり方や背景、そして風習が薄れていった理由までを分かりやすくまとめます。
砂糖を付ける——どの場面で、どれくらい渡していたのか
1. 立飯(たちはん/お葬式前のお弁当)に「砂糖1kg」
通夜・葬儀の前後に、手伝いの方や近しい人へ振る舞う立飯。
この立飯には砂糖1kgを添えるのが一般的でした。短い休憩の合間に食べるお弁当とともに、**「今日はありがとう。甘いもので疲れを癒して」**という心尽くしの品だったのです。
2. 仕上げ膳(葬儀後のねぎらい膳)に「砂糖2〜3kg」
葬儀が無事に終わったあとに振る舞う仕上げ膳には、より厚いお礼の意味で砂糖2〜3kgが添えられました。長時間にわたり動いてくださった**組内・講組(地域の手伝い組)**をはじめ、親族・ご近所の方へと配られ、ご縁を“甘く”結び直す象徴でもありました。
どのように配った?——熨斗箱と「盛下げ」
- 砂糖は**熨斗箱(のしばこ)**におさめ、**礼儀を整えた“お土産”**として渡すのが作法。
- 葬儀が終わると、盛下げ(もりさげ)の品と合わせて各自が持ち帰るのが通例でした。
- ただし、2〜3kgの砂糖はとにかく重い。徒歩や自転車で来られる方も多かった時代、**「ありがたいけれど持ち帰りが大変」**という声もしばしば聞かれました。
なぜ“砂糖”だったのか——地域の記憶と暮らしの理(ことわり)
- 価値ある保存食:砂糖は日持ちがして、家事にも料理にも使える“実用的な贈り物”。
- 甘味=ねぎらい:体力を使う葬送手伝いの疲れを癒やす象徴として最適。
- 生活の助け:当時は物資感覚がいま以上に**“ご近所で回る”**時代。
**「お葬式に行けば会葬品でのし袋を頂き、また砂糖も貰うため、プライベートでのし袋と砂糖は買う必要がなかった」**という話が残るほど、暮らしに根づいた循環でした。
こうした風習は、**“手間を惜しまない地域の助け合い”そのもの。砂糖は、単なる甘味料以上に、「気持ちを形にする」**品だったのです。
風習が薄れていった理由
- 葬儀会館の普及
自宅・寺院中心から会館中心へ。配る・持ち帰る手間を減らし、会葬品を定型化する流れが広がりました。 - 生活様式の変化
車社会・小世帯化・共働きの増加で、重い手土産は負担に。のし箱+大袋砂糖という形式が暮らしに合わなくなりました。 - 会葬返礼品の多様化
日用品・食品・カタログギフトなど、軽くて持ち運びやすい品が主流に。保管場所や嗜好の変化も後押ししました。 - 役割が“気持ち中心”へ
形よりも気持ちを簡潔に伝える傾向が強まり、砂糖という“定番”は次第に姿を消していきました。
こうして、福山市でも**「砂糖を付ける」文化は時代とともに薄れ、忘れられつつある**のが実情です。
用語ミニ解説
- 立飯(たちはん):お葬式前に葬儀に携わった方へのお弁当。昔は砂糖1kgを添えた。
- 仕上げ膳:葬儀後のねぎらい膳。砂糖2〜3kgを添えるのが一般的だった。
- 組内・講組:地域で助け合う手伝い組。葬儀運営の実働部隊。
- 熨斗箱:のし紙付きの箱。礼を尽くす贈答箱として砂糖を納めた。
- 盛下げ:式後にそれぞれが持ち帰るお供えの取り分。砂糖もこれに合わせて持ち帰った。
おわりに——“甘さ”がつないだご縁
砂糖の袋に込められていたのは、労をねぎらう優しさと、ご近所同士の支え合いでした。形は変わっても、
「手伝ってくれて、ありがとう」
という心は、今も私たちの中に生きています。
福山市の葬送文化を知ることは、地域の記憶を手渡すこと。次の世代へ、“甘いご縁”の物語を静かに伝えていきたいものです。








