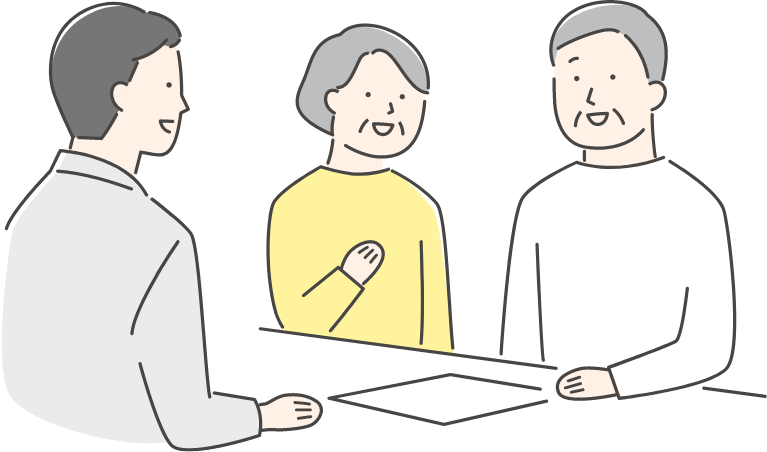
1分ですぐわかる
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
Q1
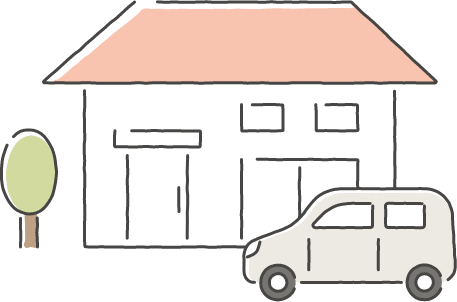
一軒家ですか?
Q2

4.5畳以上の部屋が
ありますか?
ありますか?
Q3
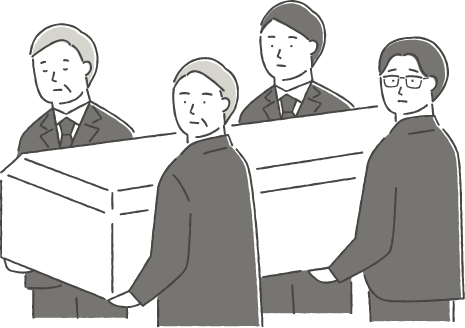
棺の出入りが可能ですか?
(棺サイズ:200cm×60cm)
(棺サイズ:200cm×60cm)
Q4
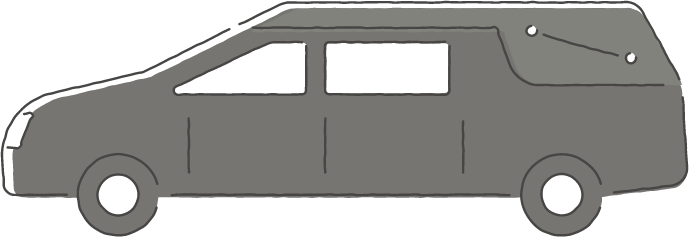
霊柩車が停められる
スペースがありますか?
スペースがありますか?
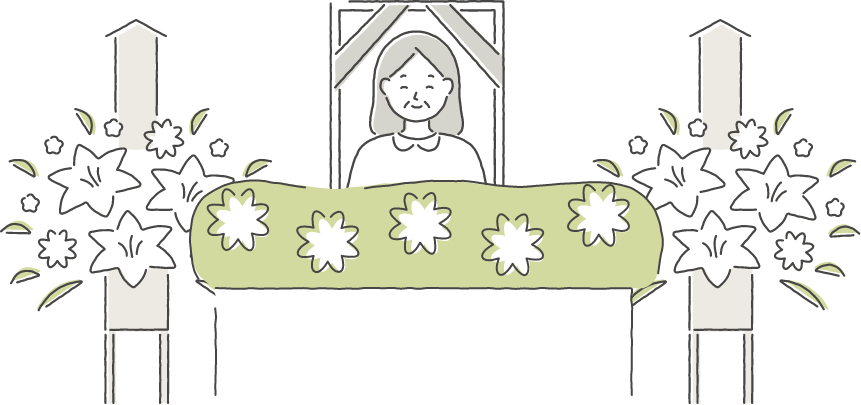
自宅葬が可能です。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

ご相談ください。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
お葬式のマナー
香典の表書きは手書き?印刷?どちらが良い?【福山市・尾道市・府中市】
2025年08月31日「字に自信がないから印刷でもいい?」「ゴム印は失礼?」――ご相談の多いテーマを、地域の実情にそってまとめました。結論から言うと、基本は“手書き推奨”。ただし、場面により印刷・スタンプ(ゴム印)も許容されます。
結論(先にサクッと)
- 原則:手書きが望ましい。 誠意と一点物の丁寧さが伝わります。
- 例外OK: 字に強い苦手意識がある、枚数が多い、会社名を整然と出したい等の事情があれば、印刷やゴム印も可。体裁と可読性を最優先に。
- 広島県(備後エリア)の基本作法: のし袋(不祝儀袋)をふくさに包んで持参し、受付で出すのが無難。県外の式に参列する際は、地域の慣習を事前確認しましょう。
なぜ「手書き」が基本なの?
“あなたから”の気持ちが伝わる
まっすぐな線や均一な太さの印字より、手書きの揺らぎに温かさが宿ります。場の空気に合う
弔事は簡素・端正が基本。筆ペンや薄墨の風合いは、静かな場と相性が良い。読みやすさの柔軟性
香典帳への転記を考えると、大きさ・バランスを調整しやすい手書きは実務的にも安心です。
ポイント:達筆でなくて大丈夫。丁寧に、ゆっくり、はみ出さずを書けば十分に整って見えます。
印刷・ゴム印が“助けになる”ケース
- 字に強い苦手意識がある:読みにくい字より、可読性の高い印字のほうが親切です。
- 大量に用意する:親族代表や会社・団体で複数枚用意する場合は、表書きのみ印刷も実務的。
- 会社名・肩書が長い:統一フォーマットの印字で整然と見せられます。
- 既製の表書き(「御香典」「御仏前」)印字袋を使う:近年は一般的。氏名だけ手書きでも十分丁寧です。
注意:派手な装飾フォント、極端に太いゴシック、朱色のスタンプは弔事に不向き。落ち着いた書体・黒インクで。
表書きと書き方(備後エリアの実情に合わせて)
- 上段(表書き)
仏式:「御仏前」(浄土真宗では「御霊前」を避けます)
初七日の包み:「初七日」
供物代など:「御供」
- 下段(氏名)
フルネーム。ご夫婦は右:夫、左:妻の並びで連名可。家単位なら**「西川家」**でも。
- 中袋(内袋)
金額(例:金壱万円也/「10,000円」でも可)、住所・氏名・電話を明記。
- 筆記具
**筆ペン(薄墨)**が無難。サインペンでも黒の落ち着いたインクを。油性ボールペンは避けましょう。
広島県(福山市・尾道市・府中市)のローカルメモ
- 弔事はのし袋+ふくさが基本。受付でふくさから外してお渡しします。
- 遠方や県外の式に参列する場合、地域・宗派の作法が微妙に異なることがあります(表書き、渡し方、受付運用など)。式場・喪家・菩提寺へ事前確認すると安心です。
NGになりがちな例
- 目立つ配色・装飾(濃い色、キラキラした紙、飾りフォント)
- にじみやすいインクジェット紙への濃すぎる印字
- 読めないほど小さい氏名・連名
- ぐちゃぐちゃな筆跡での無理な毛筆体
- 朱肉・朱色インクのスタンプ押印
迷ったらこの手順
- 表書きを決める(例:御仏前/初七日)
- 氏名を下段に(家・連名の判断も)
- 中袋に金額・住所・氏名
- ふくさに包む
- 式場の受付でふくさから出してお渡し








