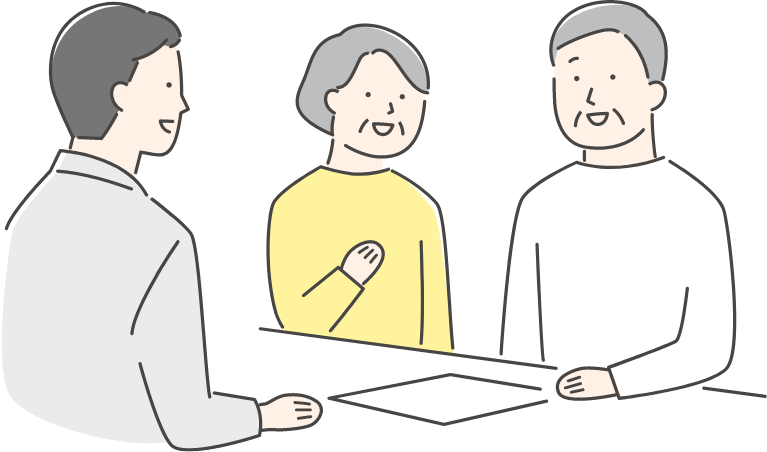
1分ですぐわかる
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
Q1
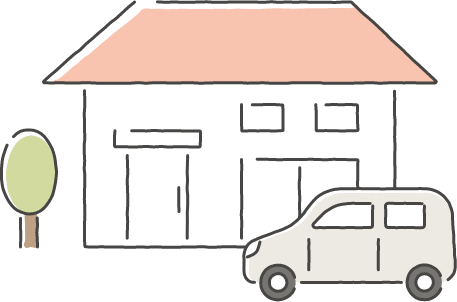
一軒家ですか?
Q2

4.5畳以上の部屋が
ありますか?
ありますか?
Q3
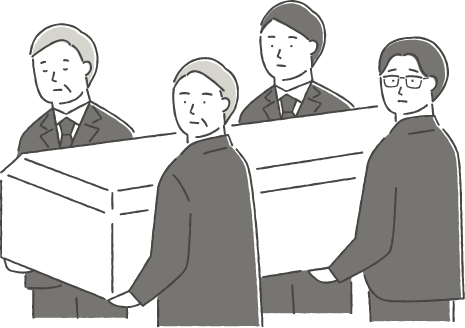
棺の出入りが可能ですか?
(棺サイズ:200cm×60cm)
(棺サイズ:200cm×60cm)
Q4
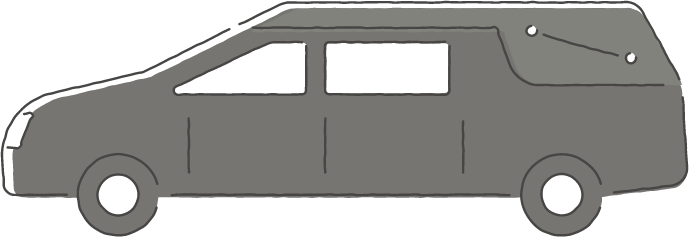
霊柩車が停められる
スペースがありますか?
スペースがありますか?
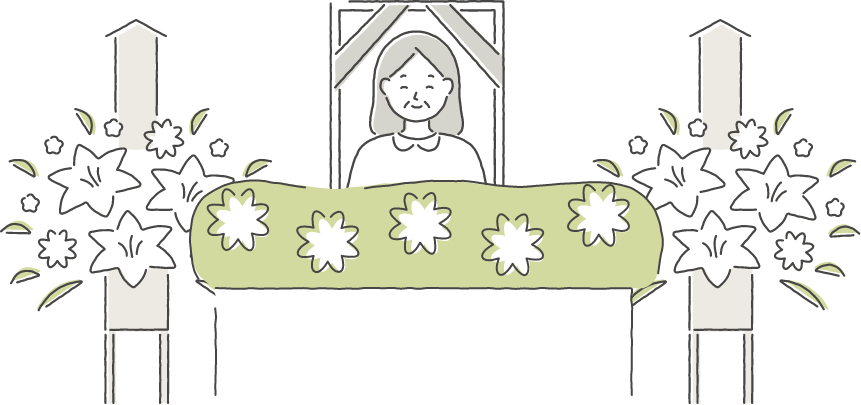
自宅葬が可能です。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

ご相談ください。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
お葬式のマナー
お葬式の遺族への声掛けのマナーは?—場面別の例文とNG表現
2025年09月01日葬儀の場で「何と声をかければいいのか…」と戸惑う方は多いもの。大切なのは、短く・静かに・相手本位。この記事では、広島県備後地域(福山市・尾道市・府中市など)の慣習にも触れながら、場面別の言い方例と避けたいフレーズ、所作のポイントをまとめました。すぐ使えるひと言テンプレもご用意しています。
まずは基本の3原則
- 短く伝える:長話は控え、要点だけを静かに。
- 詮索しない:原因や経緯、治療の話題に踏み込まない。
- 相手本位:伝えたいことより、遺族の負担にならない配慮を優先。
場面別|そのまま使える声掛け例
1) 訃報を受けた直後(電話・メッセージ)
- 「突然のことで言葉もありません。心よりお悔やみ申し上げます」
- 「ご家族の皆さまのお疲れが心配です。何か私にできることがあればお知らせください」
- ※電話は長くしない、メッセージは深夜早朝を避ける。詳細を質問しない。
2) 通夜の受付・会場で
- 「このたびはご愁傷さまでございます。お疲れのところ失礼いたします」
- 「寒暖差もございます。どうかご自愛ください」
- ※合掌・一礼を丁寧に。握手や過度な肩叩きは控える。
3) 焼香後・祭壇前から離れる時
- 「安らかなお眠りをお祈りします」
- (浄土真宗の多い地域では)「心よりお悔やみ申し上げます。ご往生をお念じいたします」
- ※宗派により「ご冥福」の表現を控える配慮も有効(迷ったら「お悔やみ申し上げます」で十分です)。
4) 出棺前
- 「本日はお見送りに参りました。皆さまどうかお体を大切に」
- ※涙が込み上げる時は、軽く会釈だけでも失礼になりません。
5) 火葬場・収骨後
- 「お疲れのところ恐れ入ります。道中どうぞお気をつけて」
- 「お疲れが出ませんように、ご無理なさいませんように」
6) 初七日・四十九日までの間
- 「本日は大変お疲れさまでした。どうかご無理のないように」
- 備後地域では葬儀当日に初七日法要を営むことがあります。香典辞退の場合は初七日も辞退されることが多いため、無理に差し出さず、声掛けはねぎらいと気遣い中心に。
7) 職場関係・近隣の方へ
- 「このたびは急なことで驚いております。仕事の段取りはこちらで調整しますので、どうぞご安心ください」
- 「家のことは気にされず、必要な時にお声がけください」
関係性別|温度感の調整
- 親しい友人へ
「ずっと支えになりたいと思っています。必要な時にいつでも頼ってください」
- 仕事の上司・取引先へ
「心よりお悔やみ申し上げます。業務は弊方でフォローいたしますので、どうかご静養ください」
- ご近所・面識が浅い場合
「このたびはご愁傷さまでございます。お力落としのことと存じます」
避けたい言葉・振る舞い(NGリスト)
- 原因を尋ねる/病状の詮索:「どうして?」「何があったの?」
- 励まし過多・根性論:「頑張って」「しっかりして」
- 価値判断:「まだ若いのに」「長生きしたから良かった」
- 説教・宗教観の押しつけ:「こうあるべき」「成仏のためには…」
- 故人比較・武勇伝:「うちの時はもっと大変で…」
- 馴れ馴れしい接触:抱きつく、肩を強く叩く など
所作と身だしなみのマナー
- 声量は小さめ、話す速度はゆっくり。
- 目線は柔らかく、相手の反応を見て早めに切り上げる。
- スマホ操作は極力控える(弔電確認など必要時は一言断りを)。
- 会場外での喫煙・飲食は指定場所で。
- 服装は控えめ・清潔感を最優先。香り(香水・整髪料)は強すぎないように。
文字で伝える時(弔電・供花カード・LINE)
- 弔電:「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。安らかなお眠りをお祈りいたします」
- 供花カード:「心よりお悔やみ申し上げます」
- LINE・メールは簡潔に:「突然のことでお力落としのことと存じます。落ち着かれた頃に改めて連絡します。どうぞご無理なさいませんように」
既読を急かさない/返信を求めない配慮を。
地域・宗派へのひと工夫(備後地域の実情に沿って)
- **浄土真宗(本願寺派等)**が多い地域では、「ご往生」「お念じします」といった言い回しが無難。迷えば「お悔やみ申し上げます」で十分です。
- 初七日を葬儀当日に営むことが多いため、当日の声掛けは「本日は通夜から初七日まで本当にお疲れさまでした」とねぎらいを重ねるのが良いでしょう。
- 香典辞退の案内がある場合、初七日も辞退されることが多いので、金封のやりとりは控え、言葉での気遣いに徹するのが安心です。
すぐ使える「ひと言テンプレ」10選
- 「心よりお悔やみ申し上げます」
- 「突然のことで言葉もありません」
- 「皆さまのお疲れが心配です。どうかご自愛ください」
- 「本日はお見送りに参りました」
- 「安らかなお眠りをお祈りします」
- 「ご無理のないように、どうか休まれてください」
- 「お手伝いできることがあれば、遠慮なくお知らせください」
- 「道中どうぞお気をつけて」
- 「本日は大変お疲れさまでした」
- 「落ち着かれた頃に改めてご連絡いたします」
よくある質問(FAQ)
Q1. 何か続けて話した方が良い?
A. いいえ。短いひと言+会釈で十分。相手が話し始めたら静かに耳を傾けましょう。
Q2. 涙で声が詰まりそう…
A. 無理に言葉を探さず、合掌・一礼だけでも失礼には当たりません。
Q3. 連絡が遅くなった時は?
A. 「ご連絡が遅くなり申し訳ありません。心よりお悔やみ申し上げます」と率直にひと言添えましょう。
Q4. 宗派の言い回しが分からない
A. 迷ったら**「お悔やみ申し上げます」**で十分です。長い言い回しは不要です。
まとめ
遺族への声掛けは、言葉の内容より「短さ」と「静けさ」、そして詮索しない姿勢が何よりの配慮です。地域や宗派の違いに気を配りつつ、相手本位のひと言を心がけましょう。








