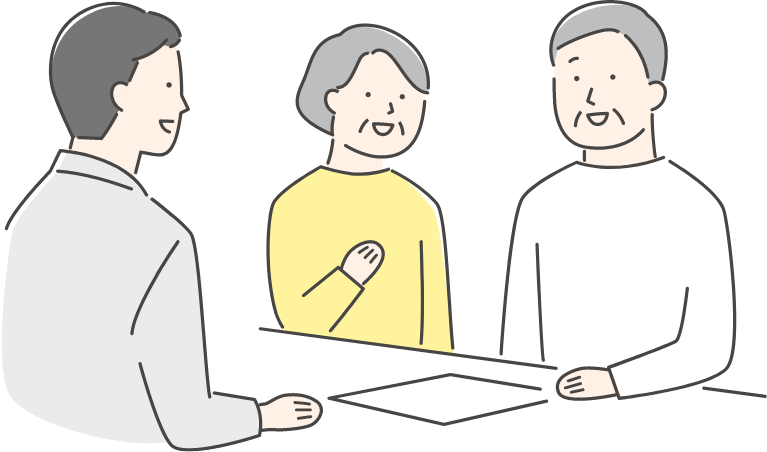
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
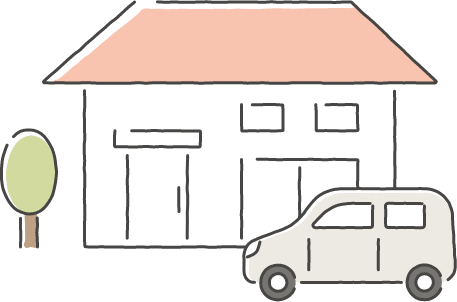

ありますか?
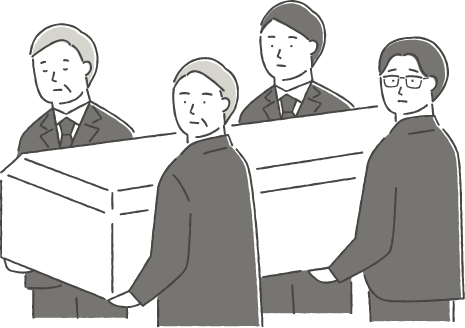
(棺サイズ:200cm×60cm)
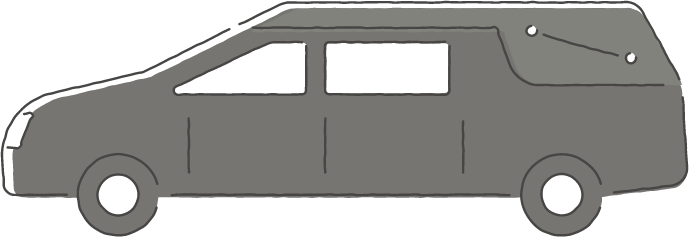
スペースがありますか?
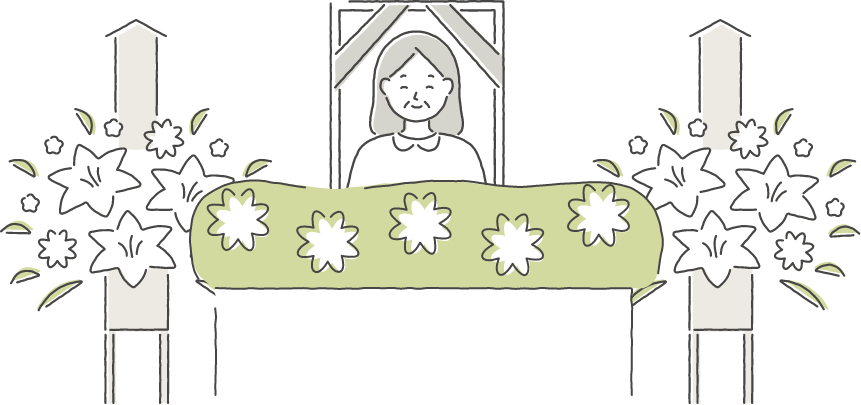
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
訃報紙(ふほうがみ)って何?
2025年05月22日──自宅玄関に貼られていた、昔ながらの葬儀の風習について
「訃報紙(ふほうがみ)」という言葉をご存知ですか?
かつて多くのご家庭で、ご家族に不幸があったことを知らせるために玄関先に貼っていた紙のことです。
現代ではあまり見かけなくなった風習ですが、そんな訃報紙の意味や役割、そして現代のお葬式との違いについてお話しします。
訃報紙とは何か?
訃報紙とは、誰がいつ亡くなったか、そして葬儀がいつどこで行われるかを記した紙で、自宅の玄関や門に貼られていました。地域によっては「忌中札(きちゅうふだ)」や「不幸札」とも呼ばれます。
内容はとてもシンプルで、たとえば以下のようなものです。
訃報
○○○○儀 ○月○日○時○分永眠いたしました
通夜:○月○日○時より
葬儀:○月○日○時より ○○斎場にて
○○家一同
地域によっては、家の前に白黒の布や「忌中」の札を立てて知らせるところもありました。
なぜ玄関に貼っていたの?
この風習には、大きく2つの意味があります。
■ ご近所へのお知らせ
昔は電話やインターネットがない時代。訃報紙は近隣住民に故人の死を知らせる大切な手段でした。葬儀の日時や場所がわかれば、ご近所の方が自然に弔問に訪れることができました。
■ 喪中を示すしるし
玄関に訃報紙を貼ることで、「いまは喪に服しています」という気持ちを外に示す役割もありました。訪問客や配達員に対し、「現在はお祝い事やにぎやかな話は控えてほしい」という意思表示でもあったのです。
現代では見かけなくなった理由
訃報紙を見かける機会が少なくなった背景には、時代の変化があります。
- 電話やメール、LINEなどで個別に訃報を伝える時代になった
- 家族葬が増え、不特定多数には知らせなくなった
- プライバシー保護の観点から、個人情報を外に貼り出すことを避けるようになった
特に都市部では、近所づきあいが希薄になり、**「知らせる必要がない」**という考え方も広まっています。
それでも、残る「気持ち」の文化
訃報紙という形式は減ってきていますが、**「周囲への礼を尽くし、気持ちを伝える」**という考え方は今も変わりません。
最近では、代わりに以下のような方法で想いを伝える方が増えています:
- 手紙やメールでのお知らせ
- 自宅に小さな掲示や案内板を設置する
- SNSでの訃報投稿(限定公開)
どんな形であれ、「ありがとう」「見送ってください」の気持ちが伝わることが大切です。
まとめ
訃報紙は、ただの「お知らせ」ではなく、故人と地域のつながりを表す、温かな風習でした。現代の暮らしの中で形は変わっても、「大切な人を失った気持ちを、丁寧に伝えること」は、これからも受け継いでいきたい文化のひとつです。
かつての風習を知ることは、今の私たちの選択をより深く、やさしくしてくれます。
心に残るお別れのために──今、あらためて訃報紙の意味を考えてみませんか?








