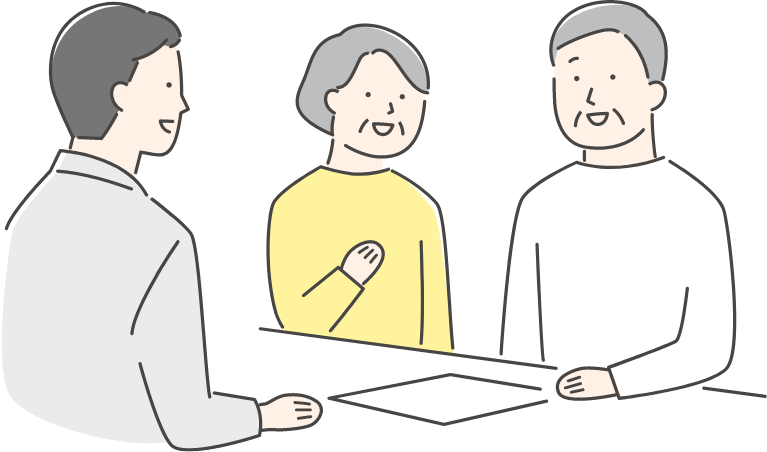
1分ですぐわかる
自宅葬の
無料診断
自宅葬ができるか悩んでる方へ
簡単な質問に答えるだけで診断できます
Q1
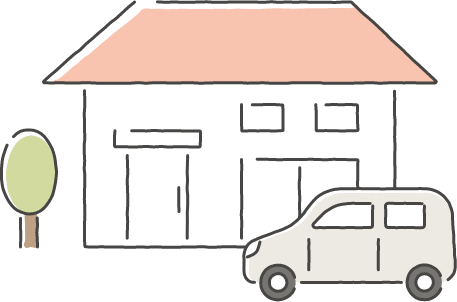
一軒家ですか?
Q2

4.5畳以上の部屋が
ありますか?
ありますか?
Q3
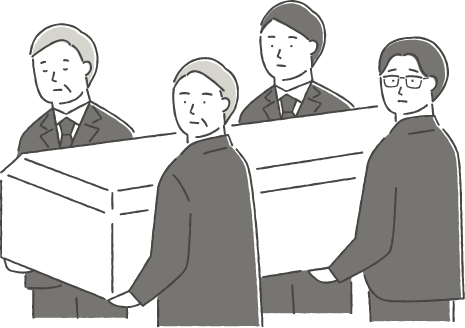
棺の出入りが可能ですか?
(棺サイズ:200cm×60cm)
(棺サイズ:200cm×60cm)
Q4
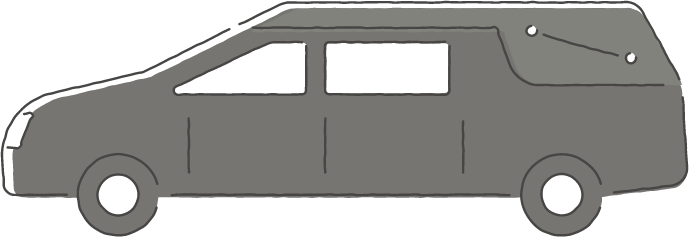
霊柩車が停められる
スペースがありますか?
スペースがありますか?
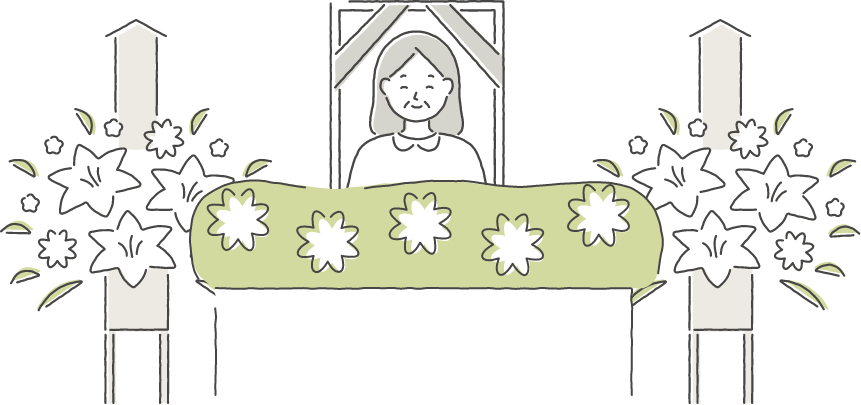
自宅葬が可能です。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。
現地でのお打ち合わせも可能ですので、
お気軽にご相談ください。

ご相談ください。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。
詳細に確認させていただきますので一度ご相談ください。サトリエでは寺院や火葬場での葬儀もご案内しております。









自宅という
特別な場所で
思い出を刻む
ひとときを。
自宅という特別な場所で
思い出を刻むひとときを。

慣れ親しんだ
自宅だからこそできる
「家族らしいお葬式」
慣れ親しんだ空間で、いつものように家族が集まり、大切な人を偲ぶ。自宅だからこそ叶う、温かな時間と心のこもったお見送りをお手伝いします。形式や宗教に縛られず、家族の想いを一番に考えたそれぞれの「家族らしいお葬式」で特別なひとときを過ごしませんか。
それぞれのご家族ごとの、自由なお葬式を

故人様が好きだった食事を持ち寄って、みんなで楽しむ。

好きな音楽を流し、故人様を想って祭壇を飾りつける手作りのお葬式。

大切な家族であるペットも、一緒にお葬式に参加できる。
自宅葬のサトリエが提案する
新しいお葬式の形

自宅葬のサトリエは、住み慣れた自宅から故人様をお送りする新しい形の葬儀を提供しています。たくさんの思い出が詰まった世界に一つのご自宅で、最後の旅立ちを提供したい。そんな想いを持ってご家族様と葬儀を作り上げていきます。
わかりやすい
料金体系

ご家族様の
想いを形に

葬儀後も
サポート


基本プラン29.8万円。
明確な料金プランで、
安心してご利用いただけます。
自宅葬のサトリエでは、花飾りや棺の種類によって4つの料金プランをご用意しています。明瞭でわかりやすい料金体系ですので安心してお任せいただけます。

FLOW自宅葬の流れ




COLUMNお役立ち情報
2025年12月13日 16時30分
お葬式のマナー
お葬式の焼香について知ろうお葬式で行われる焼香は、日本の葬儀において重要な儀式の一つです。初心者の方にとっては、その意味や作法がよくわからないということもあるかもしれません。この記事では、焼香の目的やその作法について詳しく解説します。焼香の目的とは?焼香とは、香を焚く行為のことで、主に仏教のお葬式で行われます。焼香には以下のような目的があります。
仏様へ焼香の香りをお供える事
故人を偲び、感謝する時間
焼香をすることで、故人への尊敬と感謝を表現することにもなります。
焼香の作法焼香には、立礼焼香、座礼焼香、回し焼香の三種類があります。それぞれの作法についてご説明します。立礼焼香立ったまま焼香台の前に行く方法です。最も一般的に行われる焼香方法で、以下の手順で行います。
一礼:焼香台へ進む前に遺族に対して一礼をします。その後、ご尊前に対して一礼します。
香を取る:右手の親指・人差し指・中指で香を取り、左手で軽く支えます。
香を焚く:香を一度、または複数回焚きます。※宗派によって異なります。
一礼:香を焚き終えた後、遺族に向かって一礼します。
座礼焼香畳の部屋などで、座った状態で行う焼香です。基本的な流れは立礼焼香と同様ですが、座り方や体の向きに注意が必要です。座礼のポイント:正座し、焼香台に向かってゆっくりと進みます。焼香を終えたら、最後にもう一度正座に戻ります。回し焼香椅子に座った状態で、焼香具が順に回ってくる形で行う焼香です。主に多数の人がいる葬儀や法要で使われます。各自の注意:焼香具が回ってきたら、立礼焼香と同様の手順で焼香を行い、次の人に丁寧に回します。
焼香の回数や方法は、宗派によって異なる場合があります。参加する葬儀社のスタッフに確認すると良いでしょう。
焼香の作法
焼香の回数は宗派によって異なります。
福山市の主な宗派の焼香回数をご紹介致します。
各宗派の焼香回数と作法
浄土真宗本願寺派… 1回 額に押し頂かない
真宗大谷派 … 2回 1度目は額に押し頂き2度目は静かに供える。
真言宗 … 3回 3度とも額に押し頂く
浄土宗 … 回数に決まり無し
曹洞宗 … 2回 1度目は額に押し頂き2度目は静かに供える。
日蓮宗 … 3回 3度とも額に押し頂く
作法はそんなに気にしなくても
焼香で大事な事は、作法よりも故人を偲び、仏様へ感謝する気持ちです。焼香後には皆様合掌を行いますが、合掌し、故人様への想いを心の中で感じて頂く時間にこそ、焼香本来の意義があります。お葬式の作法や仏事についても、いつでもご相談承ります。
24時間365日対応しておりますので、ご遠慮なくご相談下さい。
自宅葬のサトリエ
☎084-999-0512
福山市瀬戸町山北458‐1
2025年12月09日 21時27分
葬儀の手続き
「うちはお寺とのお付合いがないけど、お葬式ってどうしたらいいの?」実はこのご相談、とても多いです。核家族化や引っ越しの増加で、“菩提寺(先祖代々のお寺)を持たないご家庭” は年々増えています。でも、お寺とのお付合いがないからといって、慌てる必要はありません。きちんとお別れをする方法はいくつもあります。この記事では、「お葬式、お付合いのお寺がいない場合はどうしたらいい?」という不安にお応えしながら、具体的な選択肢や考え方をわかりやすくまとめました。1.まず知っておきたいこと「お寺がない=お葬式ができない」ではない
「お寺がないとお葬式ができない」と思っておられる方は多いですが、実際には以下のようなパターンがあります。
葬儀社からお寺(僧侶)を紹介してもらう
自分で近隣のお寺に依頼する
無宗教形式の葬儀を行う
火葬式のみで見送る(お経や読経はなし)
つまり、お寺とのお付合いがないからといって、お葬式自体ができないわけではありません。「どんな形で見送りたいか」を決めるところから始めれば大丈夫です。2.まずは葬儀社に相談するのが安心身内が亡くなった直後は、気持ちも動揺し、冷静に考えるのが難しいもの。「どのお寺に頼めばいいのか」「宗派はどうしたら…」と、一つひとつ自分たちで探すのは大きな負担です。そこでおすすめなのが、まず葬儀社に相談することです。葬儀社にはこんな相談ができます。
「お付合いのお寺がないのですが、お葬式はできますか?」
「宗派は特にこだわりがないのですが、どうしたらいいですか?」
「菩提寺らしいお寺が昔あったかもしれませんが、わからないです」
多くの葬儀社は、提携しているお寺・僧侶 がいます。宗派の希望を聞いたうえで、読経や戒名(法名)をお願いできるお寺を紹介してくれます。
ポイント:
「お布施の目安はいくらくらいですか?」
「葬儀後の法要などもお願い出来ますか?」
「納骨堂などのご相談も可能ですか?」
なども、遠慮なく事前に確認しておきましょう。
3.菩提寺がない場合の「お寺の選び方」「せっかくなら、今後もお付き合いできるお寺を探したい」という方もおられます。その場合、次のような点を意識してお寺を選ぶと安心です。① 通いやすさ・立地
自宅やお墓から通いやすい場所か
高齢になってからも無理なく足を運べる距離か
② お寺の雰囲気・住職との相性
話を丁寧に聞いてくれるか
専門用語ばかりでなく、わかりやすく説明してくれるか
ご家族の事情(家族葬や小規模葬など)を理解してくれるか
③ 費用や今後のお付合いについて
お布施の目安を教えてもらえるか
法事や年忌のお参りのスタイル・頻度はどうか
檀家になる場合の条件や費用はどうか
一度お話を聞きに行き、「このお寺なら相談しやすい」と感じられるかどうかは、とても大切なポイントです。4.宗派がわからない・こだわりがない場合「ご先祖の宗派がわからない」「特に宗派にこだわりはない」というケースも珍しくありません。その場合の考え方としては…
葬儀社に相談し、一般的によく選ばれている宗派・お寺を紹介してもらう
今後、自分たちがお付き合いしていきたい宗派を選び、そのお寺にお願いする
宗教色の強くない、シンプルな葬儀(読経あり・戒名なし、など)を相談する
大切なのは、**「故人と家族が納得できるかどうか」**です。形式に縛られすぎず、「この形なら心から送り出せる」と感じられる方法を選びましょう。5.お布施・費用面で気をつけたいことお寺とのお付合いがない方にとって、一番不安なのが「お布施はいくら必要?」という点かもしれません。事前に必ず確認しておきたいこと
お布施の「目安金額」を聞いておく
戒名(法名)の有無や、その際の費用の目安
お車代・御膳料(会食がない場合)の扱い
葬儀後の法要(四十九日、初盆、一周忌など)をお願いする場合の費用感
金額は地域やお寺によって幅がありますが、「相場がわからないまま、あとで驚く」 という事態は避けたいところ。葬儀社かお寺のどちらかに、勇気を出して事前確認しておくのがおすすめです。6.無宗教葬という選択肢もある「宗教色をあまり出したくない」「読経や戒名よりも、故人の音楽や思い出を中心に送りたい」そんな場合は、無宗教葬(自由葬) という形も選べます。無宗教葬の特徴は…
お経や読経が必須ではない
音楽や映像、手紙の朗読など、自由な構成ができる
宗派やお寺とのお付合いにとらわれない
一方で、
後々「やはりお墓や供養のことを考えると、お寺とのつながりも持っておけばよかった」と感じる方もおられます。
無宗教葬を選ぶ場合も、「その後の供養をどうしていきたいか」 という視点を持っておくと安心です。7.できれば「事前相談」がおすすめ身内が亡くなってから、短い時間の中でお葬式の形式・葬儀社・お寺・費用…すべてを決めるのは、本当に大変です。お寺とのお付合いがないご家庭こそ、「もしもの時のために、事前に相談しておく」 ことをおすすめします。事前相談でわかること
自分たちに合ったお葬式の規模や形式
地域の相場感(葬儀費用・お布施)
お寺の紹介の有無・費用
自宅葬・家族葬・火葬式など、それぞれの違い
相談したからといって、必ずそこに依頼しなければならないわけではありません。まずは情報を知ることが、いざという時に慌てない一番の備えになります。8.まとめ:お寺がなくても、納得のいくお別れはできる
お付合いのお寺がなくても、お葬式はできます
まずは葬儀社に相談し、お寺や葬儀の形式を一緒に考えてもらいましょう
菩提寺がない場合は、「通いやすさ」「住職との相性」「費用」を意識してお寺を選ぶ
宗派にこだわりがない場合や、無宗教葬という選択肢もあります
お布施や今後の法要については、必ず事前に目安を確認する
できれば、元気なうちに事前相談をしておくと安心
「お寺がないからどうしよう…」という不安を、一人で抱え込む必要はありません。わからないことは、葬儀の専門家に相談して大丈夫です。ご家族らしい形で、大切な人をきちんと送り出すために。早めに情報を知り、少しずつ「わが家のお葬式」をイメージしてみてください。
2025年12月09日 19時54分
お葬式のマナー
1.そもそも「家族葬」とは?家族葬とは、その名の通り家族やごく親しい人だけで行う小さなお葬式のことです。一般的なお葬式のように、会社関係やご近所、友人知人を広くお呼びするのではなく、
ご家族
ご親族
本当に近しい友人
など、10~30名ほどの少人数でお別れの時間を持つスタイルが増えています。「自分たちのペースで、ゆっくりお別れをしたい」「弔問客への対応に追われるより、家族の時間を大切にしたい」そんな想いから家族葬を選ばれる方が多くなっています。2.家族葬の流れは、一般葬とほぼ同じ家族葬だからといって、お葬式の基本的な流れが大きく変わるわけではありません。多くの場合、
ご安置
納棺
通夜式
告別式
火葬
初七日法要(地域によっては当日)
といった流れで行われます。違うのは「規模」と「招く範囲」です。儀式自体は一般葬と同じように、読経や焼香、お別れの花入れなどを行いますが、
弔問客が少ないため、進行が落ち着いている
挨拶回りや返礼品の準備が少なく、身体的・精神的負担が軽い
という点が、家族葬ならではの特徴です。3.小規模なら「自宅での家族葬」という選択肢も最近は、**ご自宅で家族葬を行う「自宅葬」**も見直されています。自宅で家族葬をするメリット
会場費がかからない
会館使用料が不要なため、トータルの費用を抑えやすくなります。
移動の負担が少ない
故人さまをご安置したまま、その場で通夜・葬儀ができるため、ご家族の移動や付き添いの負担が軽くなります。
住み慣れた場所で見送れる
長年過ごしてきたご自宅で、写真や思い出の品に囲まれながらお見送りができます。
自宅葬は何人くらいまで可能?
間取りにもよりますが、
4~5名程度なら6畳一間でも十分実施可能です。
10名前後であれば、隣の部屋やダイニングを控え室として使うなどの工夫で対応できる場合も多いです。
「家族だけで静かに見送りたい」「足腰が弱く、会館までの移動が大変」そんなご家族には、**自宅での家族葬(自宅葬)**はとても相性が良い選択肢です。4.家族葬と「直葬」はどう違うの?よく混同されるのが、**家族葬と「直葬(ちょくそう)」**です。それぞれの違いを整理してみます。直葬とは?
直葬とは、通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬のみでお見送りする形のことをいいます。■ご安置 → 火葬 → 骨上げ
という、最もシンプルな流れになるのが一般的です。
火葬の前にごく短いお別れの時間を設けることもありますが、
いわゆる「お葬式(葬儀・告別式)」は行いません。
家族葬と直葬の主な違い
それぞれにメリット・デメリットがあります。家族葬のメリット
儀式としてのお葬式をきちんと行える
ゆっくりお別れする時間が持てる
家族の想いをカタチにしやすい
家族葬の注意点
直葬に比べると費用はかかる
招かなかった方への事後報告や挨拶が必要な場合もある
直葬のメリット
費用負担を抑えやすい
式の準備や挨拶などの負担が少ない
直葬の注意点
「もっときちんと送り出してあげればよかった」と後から悔いが残る方もいる
後になってお別れ会や法要を開くと、結果的に負担が増えることも
費用だけで選ぶのではなく、
「自分たちはどのようにお別れしたいか」
「故人ならどんな形を望んだだろうか」
という視点で、家族葬・直葬・自宅葬などを比較検討することが大切です。5.こんな方には「家族葬+自宅」というスタイルがおすすめ次のようなご希望があるご家庭には、**自宅での家族葬(自宅葬)**が特に向いています。
参列者は家族と近い親族だけの予定
「住み慣れた家から見送ってあげたい」という思いが強い
高齢のご家族が多く、会館までの移動が負担になりそう
会場費を抑えながらも、きちんとした儀式は行いたい
故人が「人に気を遣うタイプで、静かに送ってほしいと言っていた」
もちろん、ご自宅の間取りや駐車スペース、近隣への配慮といった点は事前に確認が必要ですが、葬儀社が動線やレイアウトを一緒に考えることで、負担を抑えながら温かいお別れの場をつくることができます。6.まとめ:家族葬は「規模」ではなく「想い」で選ぶ時代に家族葬は、
小さな規模
身内中心
落ち着いた雰囲気でのお別れ
というイメージが強いですが、本当に大切なのは「どれだけ心を込めて見送れるか」です。
会館での家族葬
ご自宅での家族葬(自宅葬)
火葬のみの直葬+後日の法要やお別れ会
選択肢が増えた今だからこそ、
ご家族の想いと、ご予算や生活環境とのバランスを取りながら、
納得のいく送り方を一緒に考えていければと思います。
2025年12月02日 10時53分
お葬式の費用
近年、「お葬式は家族葬で」と希望される方が一気に増えました。
昔ながらの、親戚一同やご近所、会社関係まで大勢が集まるお葬式から、ごく近い家族中心の小さなお葬式へと形が変わりつつあります。
では、なぜ多くの人が「家族葬を希望したい」と考えるのでしょうか。この記事では、実際によく聞かれる家族葬を選ぶ理由・背景・本音を、いくつかの視点から整理してご紹介します。1.「ゆっくりお別れがしたい」という気持ち
家族葬を希望される方の一番多い理由が、**「人をたくさん呼ぶよりも、家族だけでゆっくり見送りたい」**という想いです。一般葬の場合は、
ご弔問に来られた方へのあいさつ
会葬者への対応
受付や会計、返礼品の準備
など、やるべきことが多く、気が付くと故人のそばで過ごす時間がほとんど取れなかったという声も少なくありません。その点、家族葬であれば、
慌ただしく来客対応に追われない
家族が故人のそばで静かに過ごせる
思い出話をゆっくりできる
といったお別れの時間を持ちやすくなります。
「形よりも、お別れの時間を大事にしたい」という方には、家族葬が合っていると言えます。
2.「故人の人付き合いが限られている」という現実
高齢化や核家族の増加に伴い、
ご近所付き合いや仕事関係のつながりが以前ほど濃くないケースも増えています。
定年退職後、会社関係のつき合いがほとんどない
引っ越しや施設入所などで、ご近所との関係が薄い
友人も高齢で、遠方からの参列が難しい
こうした状況では、「たくさんの人を呼ぶ一般葬」そのものが現実に合わず、**“自然な流れとして家族葬”**という選択になることがよくあります。「無理に大人数を集めるより、今関わっている家族で見送ろう」という考え方が、家族葬の広がりを支えています。3.費用面の不安から「規模を小さくしたい」
もちろん、葬儀費用の不安も大きな理由のひとつです。
年金生活で大きな出費が心配
子ども世代にも負担をかけたくない
「見栄」ではなく、身の丈に合ったお葬式にしたい
こうした気持ちから、「最初から家族葬という小さな規模で考えたい」というご相談が増えています。家族葬にする際の注意点!
多くの方が選ばれている家族葬。しかし選ぶ際にも注意をしないと思わぬトラブルに巻き込まれる事も…家族葬にした場合の注意点もご紹介します。
1,葬儀後にご自宅に訪問される方も増える。
家族葬にした場合、家族中心のお葬式になる分、終わった後の弔問者が増える場合もあります。地域のコミュニティが希薄になりつつある現代において、昔ほどトラブルはなくなりましたが、それでも一般葬する場合よりも、後からの弔問者が増えるケースはまだまだございます。
香典辞退をした場合に香典を持参された方にお断りをするのも大変ですので、事前に家族と相談の上、決められる事が望ましいです。2,供花が少なくなる
参列者が少ないと、それに伴いお供えのお花も少なくなります。
故人がお花が好きだった方だったり、祭壇周りを華やかにしようと思われる方であれば、お花を当家の負担でお供えしたりして、かえって当家の負担が増える場合もあります。3,葬儀費用の負担が増える場合も…
お葬式費用には「葬儀基本料金」「会場費」「搬送料金」「お布施」「火葬料」「料理・返礼品」と決して安くない費用が必要となります。
その支払いを当家の資産や香典でまかなうようになりますが、家族葬にした場合、香典収入が少なくなりますので、家族葬にして全体的な葬儀費用が安くなっても、当家が負担する費用は増えてしまうケースもあります。家族葬にする場合の、トラブルを避けるコツについてご紹介します。
1,一般弔問者のお別れの時間を設ける。
お若い方や、お顔が広い方で生前沢山のお付合いをされていた方が家族葬にした場合に、一般弔問者のお別れの時間を設ける事により、トラブルを避けられる事もあります。
例えば、通夜や葬儀の時間の1時間前にお別れの時間を設定し、一般の方は開式までの時間で受付やお別れの時間を設けて、式自体は家族中心で行うという方法です。それにより、一般の方の対応をいっぺんに終わらせる事により、後々の対応を少なくする事が可能です。またお知らせは、町内の回覧板や新聞のお悔み欄掲載(基本無料)でお知らせする事で、負担なく周知する事が可能です。
2,供花だけでもお供えして頂く
家族葬=供花辞退 というわけではありません。供花はお供えされる方の気持ちであったり、会社の規定で決まっている場合もあります。供花はお別れの際に故人へ手向けて頂けるお花として利用できますので、供花だけでも頂くというのも方法です。3,葬儀の場所を工夫する
葬儀場を使用した場合、「会場費」や「祭壇使用料」などの費用が発生します。
例えば、住み慣れたご自宅やお寺を利用する事で、費用を大幅に削減する事が可能です。
例えば自宅であれば、お仏壇を利用し葬儀空間を作る事も出来ますし、お寺であれば、ご本尊がすでにありますので、新たに祭壇を設置する事もありません。
また、会場費も自宅であれば必要ありませんし、お寺でも檀家(門徒)限定にはなりますが、葬儀会場を利用するほど必要ないケースがほとんどです。まとめ
家族葬は現代のニーズにあったお葬式スタイルではありますが、いくつかの注意が必要です。しかし工夫次第で十分対応も可能です。
まずは家族と話し合い、悔いの無いお別れをする事が大切です。お葬式の相談は24時間365日いつでも対応しております。
どんな些細な事でもかまいません。
いつでもご相談下さい。
自宅葬のサトリエ
☎084‐999‐0512
福山市瀬戸町山北458-1
2025年12月01日 21時32分
お知らせ
2025年11月30日に福山市沼隈町の浄土真宗本願寺派の寺院、南光坊様にて門徒様向けに寺院葬の説明会をさせて頂きました。寺院葬とは、お寺の本堂で執り行うお葬式です。20年くらい前まではよくお寺を利用してお葬式を行っておりましたが、会館でお葬式を行う事が増えて、次第に忘れさられてきた、お葬式のカタチでもあります。しかし、昨今のお葬式は家族親族が中心の、いわゆる家族葬が一般的になっております。
それゆえ広い会場は必要とせず、お寺であれば費用も抑えてお葬式が可能です。また、お寺でお葬式を行う場合、祭壇が必要ありません。なぜならお寺にはすでにご本尊様があり、必要以上に飾りを行わなくとも十分なお弔いの空間があるからです。
説明会では、約20分程度の説明と、15分程度の質疑応答を行い、皆様も真剣に聞いて頂き非常にありがたかったです。お寺は皆様が考えている以上に開けた場所です。お寺とご縁があり、お葬式を心配されている方は、ぜひご住職にご相談される事をおすすめ致します。
2025年11月19日 17時14分
お葬式のマナー
お葬式の準備をしていると、たまに相談として出てくるのが、
「遺影写真って、絶対に用意しないといけないの?」というご相談です。
最近は家族葬や直葬など、お別れの形が多様になり、「写真はなくていいかな…」と思われる方も増えています。このブログでは、
遺影写真の意味・役割
遺影写真が「必要な場合」と「なくてもよい場合」
遺影写真を用意するメリット
写真を選ぶときのポイント
を順番にお話しします。
1. 遺影写真ってそもそも何のためにあるの?遺影写真は、単なる「飾り」ではなく、
お葬式のあいだ、そして法事や仏壇の前で、
**故人さまの姿を思い出す“よりどころ”**のような役割を持っています。
参列者が「この方のお見送りなんだ」とわかる
表情や雰囲気から、その人らしさを感じられる
法事やお盆・お彼岸のたびに、姿を見ながら手を合わせられる
特に、最近はお付き合いの範囲が広く、「顔はあまり存じ上げないけれど、家族としてご縁があった」という参列者も少なくありません。そういう時、遺影写真があることで、参列する人も気持ちの整理がしやすくなります。2. 遺影写真は“絶対に”必要なの?結論から言うと――法律で決まっているものではありませんので、「絶対に必要」というわけではありません。ただし、次のような点を一度考えてみることをおすすめしています。遺影写真を用意することが多いケース
通夜・葬儀に、親族以外の参列者も来られる
法事やお盆など、今後も仏壇で手を合わせる機会が多い
故人さま本人が「この写真を遺影で使って欲しい」と話していた
こういった場合は、遺影写真を用意するご家族がほとんどです。遺影写真を省略することもあるケース
火葬のみの 直葬・火葬式
自宅に仏間がなく、先祖の遺影を飾る習慣がない
故人さまが、生前はっきりと「写真は出さないでほしい」と話していた
このように、ご家族の考え方や、お葬式の規模・スタイルによって決めて構わないものです。3. 遺影写真を用意するメリット「なくてもいい」とは言っても、遺影写真を用意することで得られるメリットも多くあります。① お別れの場が“その人らしく”なる
笑顔の写真や、好きな服装の写真を選ぶことで、式場や自宅の一角が、一気にその方らしい雰囲気になります。「おじいちゃん、こんな顔してたね」「このジャケット、よく着てたよね」そんな会話が自然と生まれ、少し気持ちがやわらぐ時間にもなります。② 遠方の親族や友人にも、面影を伝えられる
久しぶりに会う親族や、古くからの友人にとっては、「最後に会った姿」から年月がたっていることも多いものです。遺影写真があることで、今の姿を知ってもらいながらお別れができ、心の区切りをつけやすくなる方も多くいらっしゃいます。③ お葬式のあとも、ご家族の心の支えになる
お葬式が終わったあと、毎日、遺影に向かって声をかけることで気持ちが落ち着く、というお声もよく聞きます。「まだそこにいてくれている」ような安心感が、ご遺族の心の回復をゆっくりと支えてくれます。4. 遺影写真が用意できないとき・迷うときは?「急なお別れで、最近のきちんとした写真がない」
「スマホの写真ばかりで、遺影に使えるかわからない」
「使いたい写真が帽子をかぶっている」
そんなときも、いくつか方法があります。① 遺影写真は最近のものでなくても良い
遺影写真は亡くなる直前の写真を使うのではなく、「その人らしい」写真を使われる事をオススメします。
なぜなら写真は故人を偲んでいただく際に最もお顔を思い出して頂きやすいものが良いからです。
例えば闘病生活が長い方であれば、最近の写真であれば、やせ細っていたり、お顔がお元気だった時と変わってしまっているケースがあります。
家族や親族にとって、一番故人らしかった写真を選ぶことで、良い思い出を語りやすく、偲ぶ場としてふさわしくなります。
② 遺影写真はスマホからでも大丈夫
遺影写真はスマホからのデータでも作成可能です。
最近のスマホであればデータ自体もしっかりとしていますので、綺麗な遺影写真を作る事も出来ます。
③写真は帽子を被っていても大丈夫!
昔の遺影写真といえばは「白黒写真」「お顔はまっすぐ」「きちんとした正装(和礼服・用礼服)というイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。
最近はもちろんカラーで作成していますし、「その人らしさ」を重視した写真を選ばれる方が増えました。
それゆえ、帽子が故人のトレードマークであれば、帽子を被った遺影写真でも良いです。
つまり遺影写真に決まりはございません。5. 遺影写真を選ぶときのポイント遺影写真を選ぶ際のポイントを、簡単にまとめます。
表情
無理な笑顔よりも、「その人らしい自然な表情」を優先
年代
家族親族など周りの方が見て違和感のない年代
服装
スーツやきちんとした服装が一般的ですが、
「この服が一番その人らしい」というものがあれば、それも候補にしてOK
画質
ピントが合っていて、顔がはっきり見えるもの
スマホ写真でも、最近のものであれば問題ないことが多いです
背景
後で加工でぼかしたり差し替えたりできる場合もあります
迷ったときは、ご家族数人で見比べて、多数決で決めるのも一つの方法です。「この写真を見ると、その人の声まで聞こえてきそう」そんな一枚が見つかれば、それが一番の遺影写真だと思います。6. まとめ:大事なのは「形」よりも「気持ち」お葬式に遺影写真が必要かどうかは、宗教儀礼やルールで決まっているものではなく、ご家族の想いと、お別れの形によって決めてよいものです。
大切なのは、「こうして送りたい」というご家族の気持ちと、「こんなふうに見送ってほしい」という故人さまの想いに、できるだけ寄りそうこと。遺影写真をしっかり用意することも、あえて写真にこだわらないお別れにすることも、どちらも間違いではありません。もし
手元の写真で遺影が作れるか心配
自宅葬や小さな家族葬の場合、遺影をどうしたらいいか迷っている
ということがあれば、葬儀社や担当者に「こんな写真しかないのですが…」と、ぜひ遠慮なくご相談ください。「遺影写真は必要?」と迷われている方の不安が、少しでも軽くなれば幸いです。












